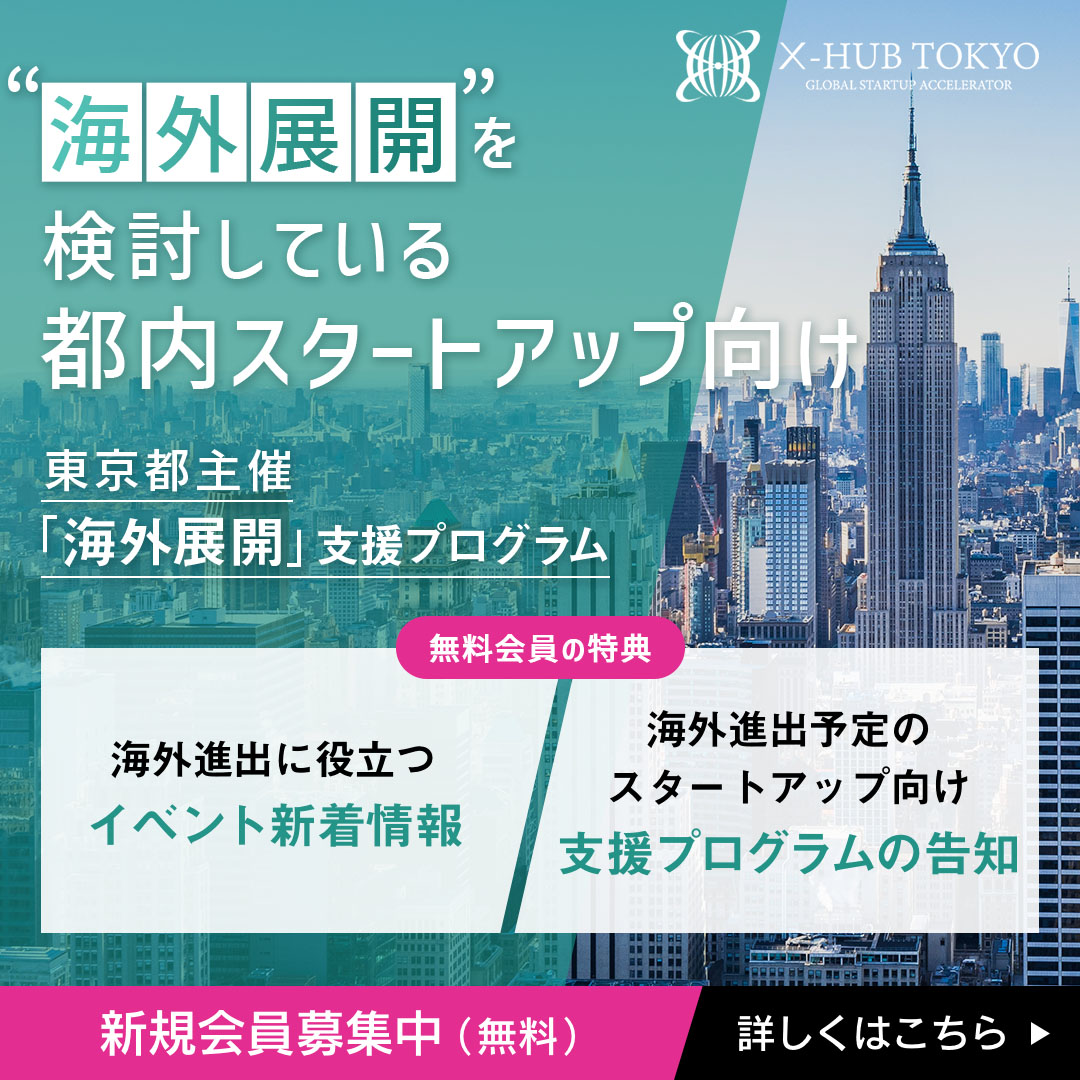世界のゲーム市場は、いまや映画や音楽を超える規模を誇る巨大産業へと成長しています。スマートフォンの普及をきっかけに利用者が急増し、現在では子どもから大人まで、あらゆる世代が日常的にゲームを楽しむようになりました。
近年はクラウドやeスポーツ、メタバースといった新領域も登場し、ゲームの役割は娯楽を超えて、文化や経済に大きな影響を与える存在となっています。本記事では、世界のゲーム市場の現状と市場規模を確認し、成長を支える要因や地域ごとの特徴、そして今後の展望について整理します。
世界ゲーム市場の現状と規模
まずは、世界全体の売上規模やゲーム別のシェア、利用者数の動向を確認し、現在のゲーム市場の全体像を把握しましょう。
最新の市場規模と推移
世界のゲーム市場は年々拡大を続けており、ゲーム・eスポーツ分野に特化した調査会社Newzooの推計によれば、2025年の市場規模は約1,888億ドル、2028年には約2,065億ドルに達すると予測されています。前年比でも堅調な成長が続いており、今後も拡大基調が維持される見通しです。
また、一部の調査機関では、新技術の普及や需要拡大を背景に、2030年前後に市場が4,000億〜6,000億ドル規模に達するとの予測も示されており、長期的にも拡大傾向が続くことが示唆されています。
新型コロナ禍による一時的な巣ごもり需要が成長を押し上げた後も、オンライン環境の普及や新興国での利用者増加が市場の底堅さを支えています。
ゲームタイプ別のシェア
ゲーム市場は現在、主にモバイル、コンソール、PCの三つの主要セグメントに大別されます。市場をけん引しているのはモバイルゲームであり、2024年の売上高は約926億ドルに達し、全体の約49%を占めています。スマートフォンやタブレットで手軽にプレイできる点が、この市場の成長を支えています。
一方、家庭用ゲーム機(コンソールゲーム)は専用の高性能ハードウェアで動作するゲームで、売上高は約525億ドル(約28%)を占めます。代表機種には、ソニーの「PlayStation」、任天堂の「Nintendo Switch」、マイクロソフトの「Xbox」などがあり、高い処理能力を活かした迫力ある映像や音響体験が可能です。
PCゲームは約432億ドル(約23%)を占め、デジタルプラットフォームを通じたダウンロード販売が主流となっています。高性能PCを利用するユーザーを中心に、高品質なグラフィックやカスタマイズ性の高さが支持されています。
なお、これらの主要区分には含まれませんが、クラウドゲーム市場は2024年時点で約22.7億ドルと推計されています。クラウドゲームとは、ゲーム処理をサーバー側で行う仕組みにより、ユーザーは高性能な機器を持たなくてもプレイできる点が特徴です。既存のモバイル・PC・コンソール市場を補完する新たな成長分野として注目されています。
利用者層と市場の広がり
世界のゲーム利用者数は2024年には約34.2億人に達し、そのうち約15.0億人が有料ユーザーと推計されています。
かつて若年層中心だった市場は、いまや30〜40代や女性層にも広がり、幅広い世代に浸透しました。モバイルゲームがライトユーザーを取り込み、多様な課金モデルが定着したことで、市場の裾野が一層拡大しています。
また、「ゲーム=子どもの遊び」という従来の認識も変化しつつあり、教育要素や健康管理機能を備えたゲームなど、日常生活に溶け込む形で進化しています。長寿シリーズの継続展開や家族で楽しめる作品の増加も相まって、世代を超えたプレイ体験が広がっています。
成長をけん引する要因と主要トレンド

続いて、ゲーム市場の成長を後押ししている技術革新やビジネスモデルの変化、そして新しい潮流を見ていきます。
モバイルとクラウドの台頭
モバイルゲームは、手軽に始められる操作性や、無料でダウンロードして必要に応じて課金する「フリーミアム」モデルの普及により、これまでゲームに馴染みのなかった層も取り込み、利用者を大きく拡大させました。
一方、クラウドゲームは誰もが「高品質なゲーム体験」を享受できる新しい仕組みです。ゲーム処理をインターネット上のサーバーで行い、映像をストリーミングするため、低スペックの端末でも最新の大作を遊ぶことができます。Microsoftの「Xbox Cloud Gaming」やNVIDIAの「GeForce NOW」が代表的で、従来の「機器を購入する負担」を軽減する点で注目されています。
eスポーツの拡大
eスポーツとは、ゲームをスポーツ競技として捉え、プロ選手やチームが大会で競い合う仕組みを指します。世界大会では賞金総額が数千万ドル規模に達するケースもあり、サッカーや野球に匹敵する人気を獲得しつつあります。
2024年の市場規模は約21億ドルに達し、観戦者数は6億人を超えたと推計されています。配信プラットフォームでの視聴が定着し、スポンサー企業も増加しており、2033年には市場規模が100億ドルを超える見通しも示されています。
新技術とビジネスモデルの進化
VRやARを活用したゲームは、ヘッドセットを装着することでプレイヤーが仮想空間に入り込んだかのような体験を可能にします。これにより、従来にはなかった没入感が実現されました。また、メタバース空間と融合したゲームでは、仮想世界での交流や経済活動が可能となり、エンターテインメントの枠を超えた新しい価値を生み出しています。
ビジネスモデルも多様化が進んでおり、サブスクリプションサービス(定額遊び放題)や、ゲーム内でのアイテム課金が主流となっています。これにより開発企業は継続的な収益を確保でき、ユーザーは多様なコンテンツを柔軟に楽しめる環境が整備されています。
地域別の市場動向と今後の展望

地域ごとに異なる市場の特徴と成長ポテンシャル、直面する課題を整理します。
北米市場の特徴
北米はコンソールゲームが主流で、マイクロソフトやソニーといった主要企業の存在感が際立っています。最新のゲーム機は映画のような映像表現や臨場感のある音響体験を実現し、質の高いエンターテインメントとして広く支持されています。
また、大作タイトルの発売に加え、オンラインサービスやサブスクリプションの普及も進んでいます。消費者は定額制で多様なタイトルを楽しむ傾向を強めており、今後も堅調な成長が見込まれます。さらに、DLC(ダウンロードコンテンツ)やバトルパス(一定期間のプレイ実績に応じて、段階的に特典が得られるシステム)など継続課金型のコンテンツが定着しつつあり、ユーザーの消費行動が多層化していることから、1人あたりの平均支出の増加が期待されます。
欧州市場の動き
欧州は、コンソール・PC・モバイルなど特定のデバイスに偏らない利用傾向があり、プラットフォームの多様性が特徴です。さらに、国や地域によって文化や嗜好が大きく異なります。一方で、課金システムに関する規制や「EU一般データ保護規則(GDPR)」に基づくデータ保護など、法制度への対応が企業にとって大きな課題となっています。
特に「ルートボックス」と呼ばれるランダム型のアイテム課金(いわゆるガチャに近い仕組み)は、未成年への影響や賭博性が指摘され、ベルギーやオランダでは禁止・制限が導入されています。
こうした状況を受け、ゲーム企業は提供確率の明示や年齢制限の強化など、透明性を高める取り組みを進めています。今後は各国の規制枠組みを踏まえつつ、ユーザーに安心感を与える公正な運営体制を構築することが求められるでしょう。
アジア太平洋地域の拡大
アジアは世界最大のゲーム市場であり、中国、日本、韓国が主要国として市場をリードしています。
中国では政府によるプレイ時間の制限などの規制が存在するものの、依然として巨大市場を維持しています。日本は任天堂やソニーなど家庭用ゲーム機メーカーの本拠地として世界的影響力を発揮し、韓国ではオンラインゲームやeスポーツ文化が深く根付き、地域全体のデジタルエンターテインメントをけん引しています。
さらに、インドや東南アジアではスマートフォン普及が新規ユーザーの拡大を後押ししており、巨大な人口基盤とインターネット浸透の拡大余地を背景に、今後最も成長が期待される地域です。通信インフラの整備やローカライズ戦略が成功のカギを握ります。
まとめ
世界のゲーム市場は2025年に約1,888億ドルに達し、2028年には2,065億ドル超へ拡大する見通しです。成長を支えるのは、モバイルやクラウドゲームの普及、eスポーツやメタバースといった新領域の発展です。北米はコンソールゲームを軸に高い収益性を維持し、欧州は規制対応と透明性の確保を重視する一方で、アジアは規模の大きさと新興国の成長ポテンシャルで際立っています。こうした変化に対応するため、企業には技術革新や法制度の動向を踏まえた戦略的な対応が求められます。
また、「スーパーマリオ」や「フォートナイト」に代表される世界的な人気シリーズは、家庭用ゲーム機やPC、モバイルなど複数の異なるデバイスで展開するマルチプラットフォーム戦略と継続的なアップデートを通じてブランド価値を高め、文化や社会への影響力をさらに広げていくでしょう。
東京都が主催する「X-HUB TOKYO」事業では、都内スタートアップの海外展開を支援しています。海外進出に必要な知識や市場情報の提供に加え、現地VCや大企業とのネットワーク構築、専門家によるメンタリングなどを通じ、グローバル市場での競争力向上を後押ししています。詳細や最新のイベント情報は、「X-HUB TOKYO」公式サイトをご覧ください。