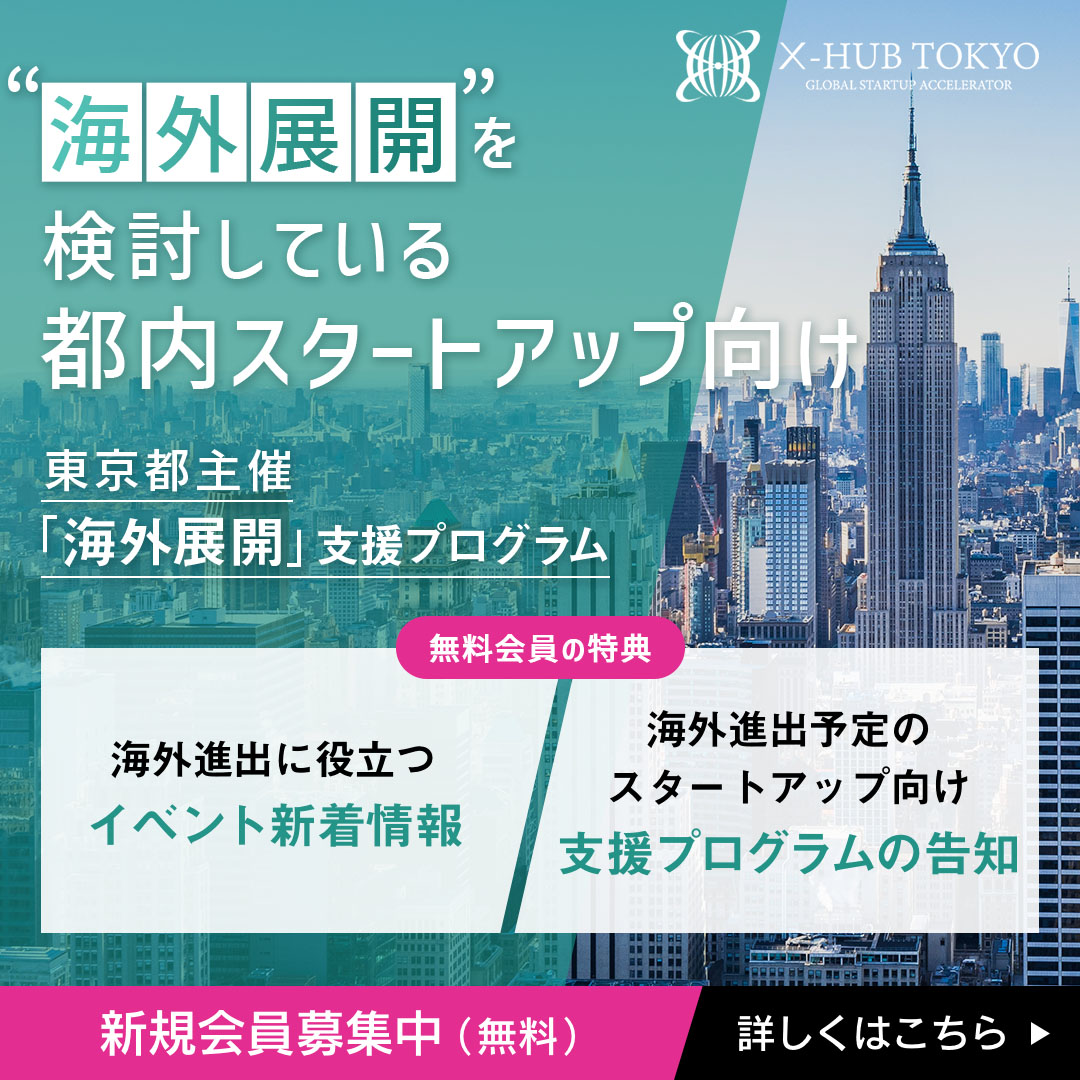日本企業の海外進出には、メリットもあればデメリットもあるものです。それぞれを比較して、海外進出を検討する材料にしましょう。
海外進出:3つのメリット
メリット1・販路拡大や市場開拓
小売やサービス、流通関連企業の海外進出でもっとも期待されるのは、販路の拡大です。海外の市場規模の拡大によって、日本国内での事業展開よりも大きな販路を獲得しやすくなります。
日本ではGDPは横ばいで、少子高齢化によって消費も停滞気味と、今後の国内市場は楽観的でない状況が続いています。一方で、海外にはまだ未開発な商品ジャンルもありますし、これから参入する余地が多く残っている市場も少なくありません。そのため、海外市場を相手にビジネス展開をすることは、国内企業の生き残りの道として注目を集めています。
近年ではEコマースやSNSの普及により、現地消費者へのアクセス手段も多様化しており、販路拡大の可能性はさらに広がっています。大企業をはじめ、中小企業・ベンチャー企業でも海外進出をする企業は増えています。
メリット2・生産コストの削減

2つ目のメリットは、コストの削減です。以前は主に製造分野において、安い労働力の獲得や国内よりも安い資材や設備、原材料などの調達を期待して海外進出を果たす企業が多く見られました。
近年では、大企業を中心に現地市場を目的とした海外進出が増えていますが、コスト削減を目指す傾向は今でも続いています。特に中小企業では、安価な新興国の商品との競争に対応するために、生産コストの削減を期待して海外に進出する企業が一定数はあるようです。
また、コスト削減の一環として、安価な部品などの現地調達を目指して元請企業が海外進出することにより、関連企業も連携して海外進出を図り、生き残りをかけるケースもあります。さらに現地調達を進めることは、為替変動の影響を抑え、調達先の多様化による供給安定化にもつながります。
メリット3・節税効果
海外に日本企業が進出するにあたっては、ビジネス展開以外にも税制面で注意すべき点があります。しかし、適切に対策を講じることで、海外進出のフェーズによっては節税のメリットを享受できることもあります。
海外でも日本と同じように利益が出れば税金がかかります。税率はそれぞれの国・地域によって異なっており、日本よりも低いこともあります。また、特に海外進出を目指す企業に向けて税制優遇を行っている国もあります。
外国企業の誘致を行っている国では、外国企業が税制面で優遇する「経済特区」制度を設けていることもあります。中国をはじめ、ベトナム、マレーシア、カンボジアなどの東南アジア諸国が経済特区を設けている国の代表例です。たとえば、ベトナムは法制度面で海外進出しにくい面もありますが、税制面では優遇されていると言えます。
ただし、日本の「タックス・ヘイブン対策税制(CFC税制)」に留意が必要です。一定条件を満たす場合には海外子会社の所得が日本本社に合算され課税されるため、専門家や公的支援機関に相談しながら慎重に判断することが望まれます。
海外進出:4つのデメリット
デメリット1・人件費の上昇
新興国の経済発展に伴い、近年人件費の上昇が顕著になっています。高度経済成長時には、新興国の安い労働力を求めて次々と海外進出を果たした日本企業ですが、近年の人件費高騰によって、事業計画の見直しや収益性の再検討が必要となるケースが増えています。
今後、新興国を中心に、以前のように安い人件費を目的として海外進出をすることは、難しくなってくるでしょう。
製造業以外でも、新興国の教育水準の向上によって、人件費の上昇は進むと見られています。IT技術などを身につけた優秀な人材を確保できる点はメリットと言えますが、高騰する人件費により、経営自体が悪化する恐れもあります。
このため、単にコストの低減を追求するのではなく、質を重視した人材活用への転換が求められています。
デメリット2・為替の変動
海外ビジネスにおいては、外国通貨建で取引を行うため、外国為替相場の変動リスクに注意が必要です。為替レートの変動によるリスクを回避することは難しく、大きな利益となることもあれば、大きな損害となってしまう場合もあります。
たとえば、円高時に国内に商品を輸入すると差益を得られますが、反対に輸出すると差損となります。円安時に自国に送金すれば差益となり、円高時には海外企業の買収や海外出店が有利です。使い方によって為替レートはこのように利益を得る手立てにもなります。
一方で、為替は変動が大きく、経営の不確実性や資金計画の立てにくさにつながるため、デメリットとも言えます。売買で利益を得ても、為替相場の変動によって損失を出してしまうこともあり、先が読めない為替相場の動きに常にリスクを負っている状態になります。
為替予約という選択肢はある一方で、相場動向のチェックは継続しましょう。特に資金基盤の小さい中小企業では、為替変動が経営に及ぼす影響が相対的に大きくなる点に留意が必要です。
デメリット3・現地での人材管理や育成の難しさ

海外進出において、特に困難を伴うのは、現地での人材管理や育成と言えるでしょう。現地の法規制によって現地人材の雇用が定められており、日本人従業員だけでは経営できない場合もあります。
現地の優秀な労働力を活用できれば理想的ですが、国民性や企業風土、働き方などが異なるため、日本式の管理方法に対して現地採用の社員が反発したり、モチベーションを低下させたりすることがあります。また、離職率の高いエリアでは雇用しても人が育つ前に辞められてしまうこともあります。
その結果、育成にかけた時間やコストが十分に回収できず、再度採用や教育を行う必要が生じる場合もあります。
デメリット4・現地の法制度や規制・経済情勢
現地の法制度や規制の複雑さ、経済情勢は海外進出のハードルを一段と高める要因です。現地の法制度次第では、参入自体が不可能な場合もあります。
取り扱う商品・サービスによっては、進出先の選定や参入方法が規制で大きく制約されることもあるでしょう。エネルギー関連、メディア、都市インフラ事業などは外資の参入が難しい分野です。小売業や飲食業でも外資比率に制限が設けられており、審査が厳しいため複数店舗の展開は容易ではありません。ベトナムでは特に飲食業や小売業分野で外資系企業の参入が難しいとされています。
このほか、多くの国・地域で製造業など特定の業種以外は、保有可能な外資比率の上限が定められています。人材面の規制もあり、従業員の外国人比率の上限や、一定数の現地雇用を義務づける国も少なくありません。たとえば、タイでは資本金の額が外国人の雇用数に応じて定められ、現地から一定以上雇用することが決められています。
さらに、知的財産権保護が十分でない国では模倣品リスクが高まり、事業継続に影響を及ぼすこともあります。最悪の場合には撤退を迫られるケースも想定されます。
海外進出のステップは、目的を明確にして情報収集を
日本企業が海外進出する際には、事前の入念な調査が必要です。目的を明確にしてから海外進出のステップに沿って調査や視察を行い、効率よく準備を行ってください。
ステップ1・海外進出をする目的の明確化
海外進出の大きなメリットには「サービス販路の拡大」や「生産コストの削減」などがあります。新市場を開拓、生産・部品や商品の調達拠点を設置するなど、まずは現在自社が必要としているものが何かを明確にしておきましょう。
その目的は国内では達成できないのか、人材や資金など自社の体制が不足していないかなど、なぜ海外進出を行うべきなのかを検討することが大切です。長期的な事業戦略を立てて売り上げや投資コスト回収年数などの具体的な目的を明確にしておくと、より確実に営業利益の確保や業績の拡大につなげられます。
ステップ2・情報収集と進出計画策定
「自社の商品・サービスはこの国に受け入れられやすいか」「消費や経済が伸びている国はどこか」など、海外進出に向けて知っておくべきことはたくさんあります。
海外進出の目的に合う国や海外進出方法などを決定、海外進出の時期や工程を計画するためには、海外進出を目指している国の経済情勢はもちろん、生活習慣や嗜好、法制度、外資規制などのビジネス背景となる調査も必要です。
政治の安定度、人件費、物流事情、他の企業の進出状況なども調べ、多角的に進出について検討しましょう。
ステップ3・市場調査
海外に拠点を設けた場合に自社の商品・サービスは現地で需要があるのかどうか、市場調査の実施はとても重要です。進出国のニーズを調査して、自社商品に適しているかどうか、また、現地に合う商品の開発を行う必要があるかなどの検討が必要になるかもしれません。
市場規模の大きさは、海外進出を目指す企業の重要な目的の1つにもあがっています。市場規模や成長性の把握など、確実な市場調査が必要です。
ステップ4・海外視察
海外進出を決める要因として、現地視察は欠かすことができないでしょう。実際に海外進出を行った企業の多くが現地調査を複数回行い、現地の市場や現地法人、店舗、不動産などをはじめ、教育機関などの生活に根差した現地情報まで確認しているようです。
現地で知人やコンサルタントなど、現地のさまざまなネットワークを持つ「現地パートナー」にサポートを依頼すると視察訪問先のアポイントが取りやすいでしょう。重要度の高い現地視察を効率よく行うことで、海外進出が成功に近づきます。
特に現地パートナーを通じてネットワークを構築しておくことは、その後の事業展開を円滑に進めるうえで重要です。また、進出後も定期的に事業モデルを見直す改善サイクルを意識することで、変化の大きい海外市場に柔軟に対応できます。
まとめ
このように、販路拡大、コストダウン、節税効果などのメリットがある一方で、為替変動、適切な人材確保の困難さ、法規制などによるリスクが大きなデメリットとして存在するのも事実です。海外進出を行う際には、こうしたメリット・デメリットを天秤にかけたうえで意思決定を行う必要があります。