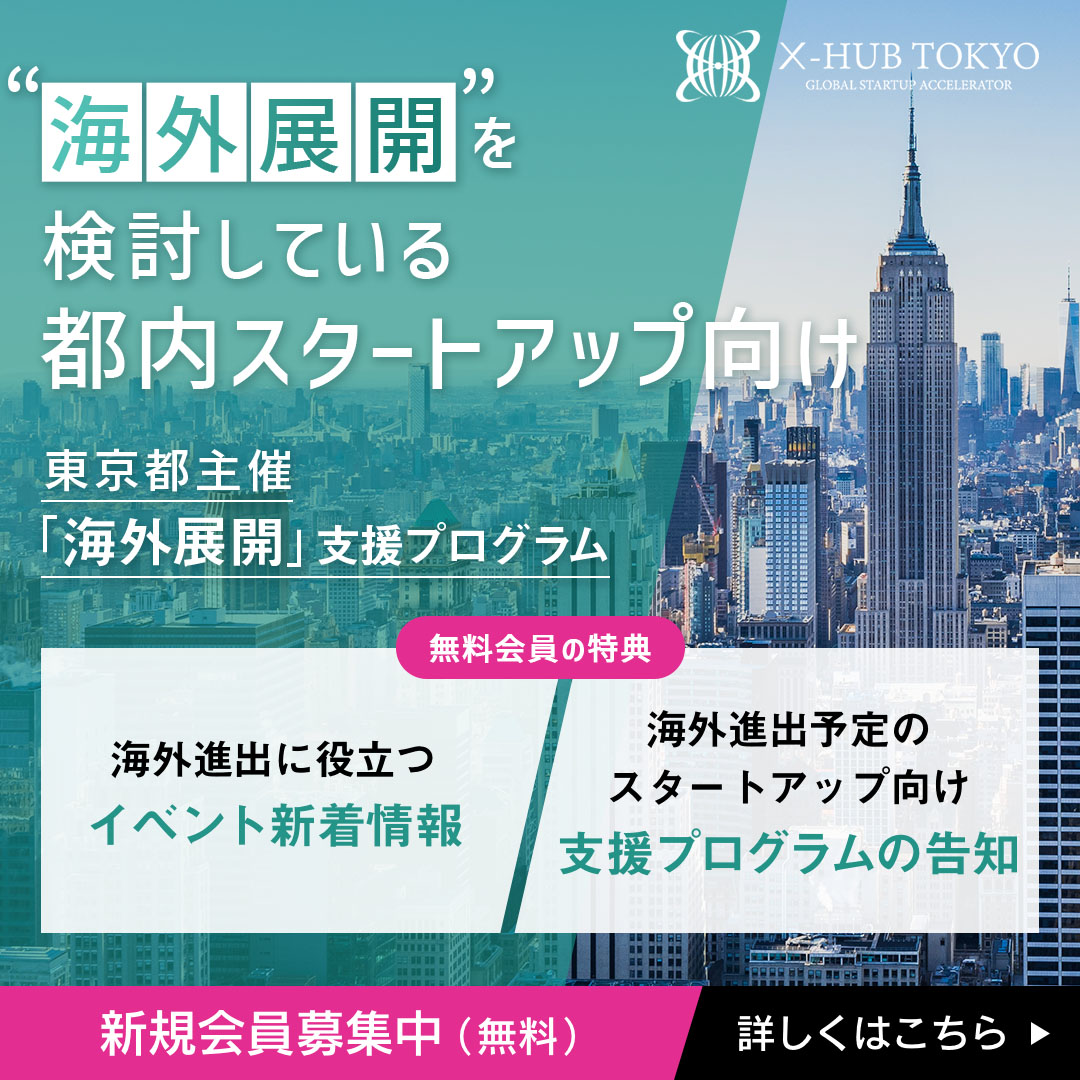誰もが知っている世界的大国である中国。中国はその成長力によってアジアをけん引してきました。これまで中国が成長してきた背景には中国が持つ国力があります。中国経済が発展してきた理由、そして中国経済の今後の見通しについて解説します。
中国経済の高度成長を振り返る
中国の急速な成長は、決して最近始まったものではありません。中華人民共和国が発足した頃から、どのように経済成長の土台が築かれていったのかを振り返ります。
南巡講話をきっかけに経済が成長
中華人民共和国建国後から1970年代までの中国経済は、実質成長率が平均で6%前後とされるものの、年ごとの変動が激しく、安定的な成長とは言えませんでした。
転機となったのは1978年、鄧小平の主導で改革開放政策が開始されたことです。この政策により、経済成長の土台が築かれ始めました。
そして、1992年の鄧小平による南巡講話で改革開放はさらに加速します。鄧小平は湖北省、広東省、上海市を約1カ月かけて視察し、各地で改革開放を呼びかけました。これを機に農村部から都市に人口の流入が本格化し、後の工業大国への進展を支えました。
市場経済のグローバル化
南巡講話をきっかけに、市場経済のグローバル化が進みました。華僑資本や外資を活用することですぐに頭角を現したのが製造業やサービス業です。WTOへも加盟をしたことで中国は世界の工場としての役割を担うようになりました。1992年からの30年ほどで米中貿易総額は200倍に拡大したのです。
中国が外貨準備高世界一になった背景
中国が世界2位の経済大国となった背景のひとつには、豊富な外貨準備高があります。外貨準備は輸入代金の支払い能力や為替の安定に対する信認の裏付けとなり、危機時の安全網として貿易・投資の拡大を下支えしました。では、この巨大な外貨準備高はどのように築かれたのでしょうか。
世界一の外貨準備高
中国の外貨準備高は2025年7月末時点で約3兆3,000億ドルに達し、依然として世界一の規模を誇ります。これは2位の日本(約1兆3,000億ドル)を大きく上回ります。
この外貨を稼いできたのが中国の工場群です。中国からの輸出を決済する場合必ず国外から外貨を送金することになります。つまり、中国では国外向けの商品を製造すればするほど、外貨として還元されるという仕組みでした。
特に途上国にとっては国際貿易をスムーズにおこなうために、ある程度の外貨準備高を蓄えておくことが重要であるといわれています。しかし、中国では外貨準備高が多い一方で対外債務も膨れ上がり、問題視する声が上がるようになりました。
また、為替相場も無視することができない要素です。GDPの計算はドルベースでおこなわれます。中国人民銀行は人民元のレートが安くなると外貨準備高として保有している外貨を売って、人民元を買ってレートを支えることになります。
この結果、2014年には4兆ドル近くあった外貨準備高が2024年には3兆2000億ドルほどに減少しました。今後また人民元が安くなれば、外貨準備高にも変動が起きることが予想されます。
中国の成長を支えた人口という財産
中国経済の急速な発展は、世界最大の人口規模に支えられてきました。その人口がどのように経済成長の原動力となったのか、そして今後の変化がもたらす課題について解説します。
2011年が生産年齢人口のピーク
中国の高度成長を支えた最大の要因は、世界一の人口規模です。特に農村部から都市部へ移動した安価な労働力は、工業化やサービス産業の拡大を後押しし、経済成長の基盤となりました。
経済産業省「通商白書2024年版」によれば、中国の生産年齢人口(15〜59歳)は2011年に約9億2,800万人でピークを迎え、その後減少に転じています。2022年には約9億1,500万人まで縮小しており、2040年には約7億8,000万人、2050年には約6億5,000万人にまで減少すると予測されています。
今後は労働力不足と高齢化の進行が同時に進むことが懸念され、社会保障や経済成長の持続性に大きな影響を与える可能性があります。
一人っ子政策の影響
2011年からの生産年齢人口の減少を加速させた大きな要因が、一人っ子政策です。1979年に導入され、2015年に廃止されるまで36年間続いたこの政策は、出生数を大幅に抑制しました。
政策廃止後には二人っ子・三人っ子政策が導入されましたが、都市化の進展や教育費・住宅費の負担増なども重なり、出生率は大きく回復していません。実際、2022年および2023年の出生数は2年連続で1,000万人を下回り、建国以来の最低水準を更新しました。
その結果、2022年には中国全体の人口が61年ぶりに減少に転じました。今後も少子高齢化の進行が続くと見込まれ、労働力の確保と社会保障の持続可能性が大きな課題となっています。
中国経済の今後
高度成長期を経て、中国経済は新たなフェーズに入っています。不安定な状況が続く現状と、政府が掲げる新たな成長戦略について見ていきましょう。
不安定な経済状況が続く
中国の経済状況は、不動産価格の下落や若年失業率の増加、節約志向の高まりから消費低迷が続くなど、2025年に入っても不安定な状態が続いています。中国国内の主要70都市の住宅価格指数は2022年から下落傾向にあり、2024年6月には前月比で新築住宅が56都市、中古住宅が69都市で下落するなど、不動産不況の長期化が懸念されます。
中国国家統計局の発表によると、2024年通年の実質GDP成長率は前年比5.0%となりました。前年からは減速したものの、政府の成長率目標である5.0%前後は達成しています。
こうした状況を受け、中国政府は2024年9月以降、金融緩和や不動産対策、株価対策に加え、特別国債の発行などによる景気刺激策を相次いで発表しました。なかでも注目されたのは、住宅購入時の頭金比率引き下げで、全国水準は1軒目が15%、2軒目が25%とされています。
中国経済の減速と「新質生産力」政策
中国の経済成長率は2023年に5.4%、2024年は5.0%と推移しました。背景には2022年頃から深刻化した不動産不況があります。しかし、成長率の鈍化は近年だけの現象ではなく、2010年頃から農村部の余剰労働力の枯渇や賃金上昇を契機に、すでに低下傾向がみられていました。
さらに2022年には61年ぶりの人口減少が始まり、少子化は想定以上のペースで進んでいます。国連の「世界人口推計2024」によると、中国の人口は2100年までに2024年比で55%以上減少する可能性があるとされています。加えて、アメリカとの貿易摩擦や安全保障重視の政策も、経済の重荷となっています。
世界経済における米中の位置関係にも変化が見られます。英シンクタンクの経済ビジネスリサーチセンター(CEBR)によると、2020年末の時点では「2028年に中国のGDPが米国を上回る」と予測されていましたが、2023年末の改訂予測では2037年とされ、逆転の時期は大幅に後退しました。
一方で、中国政府は経済成長の新たな柱として「新質生産力」の育成を掲げています。これは「高度な技術」「高効率」「高品質」を備えた先進的な生産力を意味し、EV(電気自動車)、半導体、再生可能エネルギー、デジタル産業などが重点分野です。2024年からは超長期特別国債の発行を進め、地方政府支援や設備投資促進を通じて産業転換を図っています。外需についても、「シリコンサイクル」と呼ばれる半導体市況の改善により輸出が好調となり、EVや鉄鋼などの低価格輸出も拡大しています。
今後の展望とリスク
国際通貨基金(IMF)の「世界経済見通し(2025年4月版)」によれば、中国の実質GDP成長率は2025年+4.0%、2026年+4.0%と予測されています。公共投資やハイテク産業の振興が成長を下支えする一方、不動産デベロッパーの経営不振や家計の信頼低下により、不動産市場の改善は当面期待しにくい状況です。
中国政府は2024年10月に、不動産市場の安定化や企業支援を強化し、介護や保育などサービス分野の消費拡大を後押しする方針を表明しました。しかし、今後の中国経済には、国内では不動産市場のさらなる悪化や地方政府の財政悪化、国外では米中摩擦や地政学的リスクなど、複数のリスクが存在します。
特に2024年11月の米国大統領選挙で再選したトランプ政権は、2025年に中国製品への追加関税を一部発動し、AIや半導体などハイテク分野でも規制を強化しました。こうした動きは中国経済に直接的な打撃を与える可能性があり、企業の海外進出や展開戦略に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。米中関係の動向は、引き続き注視すべき重要な要素といえるでしょう。
まとめ
中国は1970年代後半から急速な経済成長を遂げ、特に1992年の南巡講話以降、改革開放政策により世界の工場としての地位を確立しました。しかし、近年は不動産不況や人口減少などの課題に直面しています。2024年の実質GDP成長率は5.0%と、かつての高成長期に比べれば低い水準となっています。
一方で、中国政府は「新質生産力」の育成や積極的な財政政策を通じて、産業構造の転換と経済の持続的成長を模索しています。世界経済における中国の存在感は依然大きく、今後も政策動向と国際関係の変化に注目する必要があるでしょう。
出典:
・ジェトロ(日本貿易振興機構)
広州市と深セン市、個人住宅ローンの最低頭金比率を引き下げ
低迷する消費、政府は設備投資・買い替え促進を中心に喚起
2025年の中央政府予算内の1,000億元を前倒し支出、内需拡大へ
・国際通貨基金(IMF)「2025年4月IMF世界経済見通し」
・経済産業省「通商白書2024」
・国連「世界人口推計2024」
・英国経済ビジネスリサーチセンター(CEBR)「世界経済リーグ・テーブル2024(WORLD ECONOMIC LEAGUE TABLE 2024)」