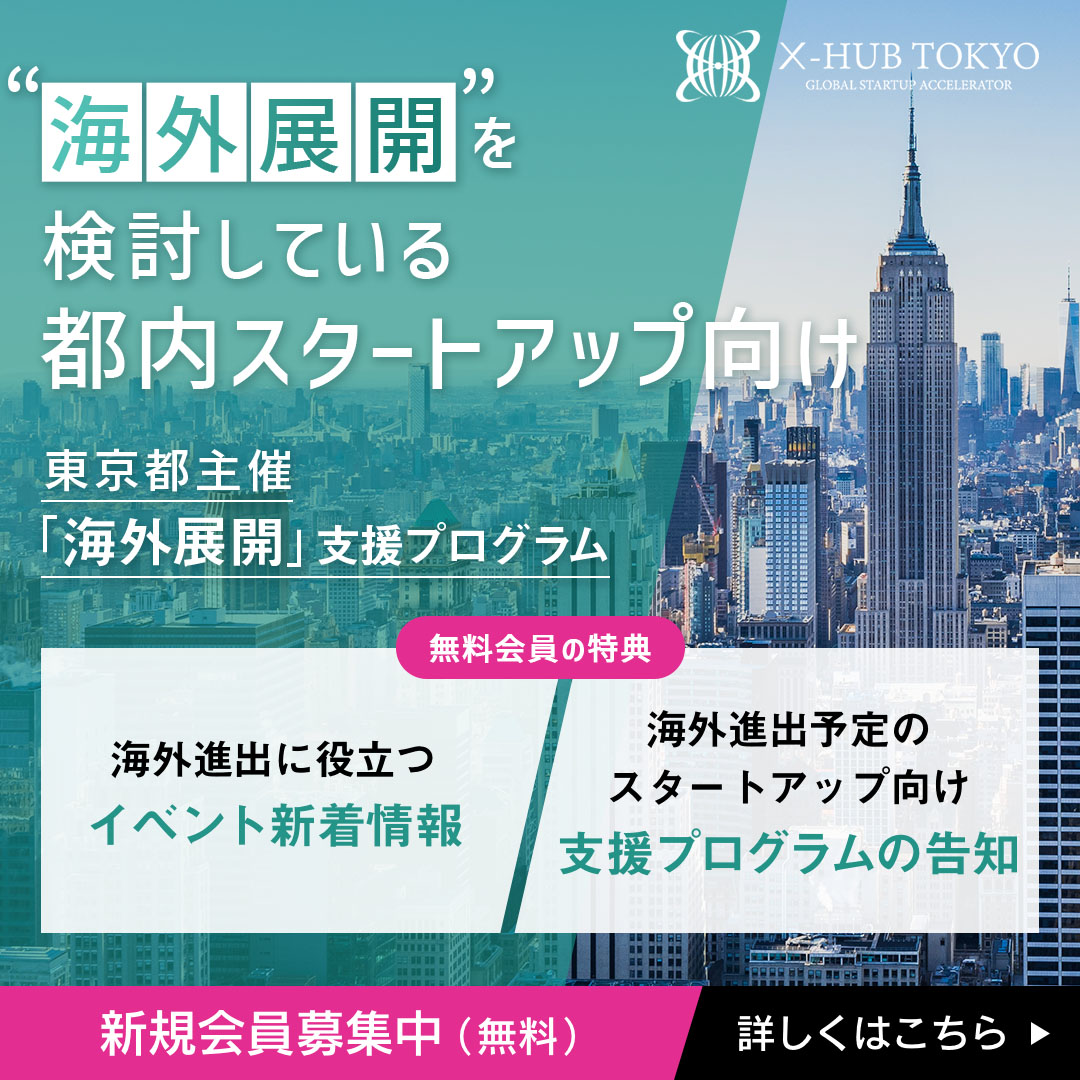海外進出で海外法人を設立する場合、問題となるのが現地で働く従業員です。多くの場合は運営の責任者や管理者として日本本社からスタッフを派遣します。その場合、雇用保険はどうなるのでしょうか。
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者の雇用安定を図り失業に備えるための保険です。
雇用保険とは
雇用保険の被保険者である労働者が定年退職や自己都合退職によって離職した場合、その被保険者であった期間や年齢に応じて、一定の額と期間の失業給付金が支給されます。また、雇用保険制度ではそれ以外にも雇用の安定に関わる給付を行っています。
早期に再就職出来た場合に給付される「就職促進給付」、求職者へ支給する失業手当や傷病手当などの「求職者給付」、再就職のための能力開発やキャリア形成を支援する「教育訓練給付」。さらに、育児や介護で休業した場合の「雇用継続給付」などがあります。
加入の対象
失業時の給付金雇用保険の被保険者となるのは原則すべての労働者で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上雇用する見込みがある場合には必ず加入しなければなりません。
企業は従業員を雇用した場合、雇用保険に加入させることとなります。ただし、海外法人からの赴任者で、海外で雇用保険のような制度に加入している人は加入免除になります。では、日本企業から海外法人に赴任する場合にはどのような扱いになるのでしょうか。
海外で働く場合のパターンと対応
海外で働くことになった場合、大きく分けて3つのパターンが考えられます。雇用保険を考えるポイントとなるのが、事業主と従業員の雇用関係です。
海外出張の場合
まずひとつ目が「出張」で海外に行く場合です。視察や商談等で出張となる場合、雇用主との関係は変わりません。そのため雇用保険も変化することなく継続します。海外進出を考えているときには、市場調査や現地のパートナーを探すために海外出張が多くなるでしょう。その他にも以下のようなケースが考えられます。
- 海外の顧客やパートナーとのビジネスを行うため
- 海外の工場や拠点を訪問するため
- 海外での新規事業立ち上げ、事業展開のための調査・打ち合わせのため
- 海外での学会やセミナーなどの学術的な目的のため
- 海外での取引先との契約締結や交渉のため
国内企業から在籍出向の場合
次に「出向」の場合です。日本の企業が海外に派遣する社員のことを指し、海外でのビジネス展開や現地スタッフの指導、市場調査や情報収集などを担当します。海外の支社などに勤務する場合は、雇用関係がそのままであれば雇用保険も変わりません。
一定期間海外の事業主で雇用されたとしても、日本の事業主の業務命令によるもので、雇用関係に変化はないからです。つまり、在籍出向である場合は、海外の法人で勤務している場合でも雇用保険の被保険者として扱われます。
海外企業に直接雇用される場合
最後に、雇用保険が適用にならない「転籍」の場合です。転籍とは、日本国内の事業主との雇用関係を終了させて、出向先の海外企業に雇用される形式です。
この場合は雇用関係が一旦終了しているため、雇用主が現地の企業となり、日本の雇用保険の被保険者資格を喪失することになります。そのため、海外での勤務期間はどれくらいなのか、給与はいくらなのか、自分にとって不利益な契約内容とならないようしっかり確認を行うようにしてください。
海外赴任者の保険料の扱い
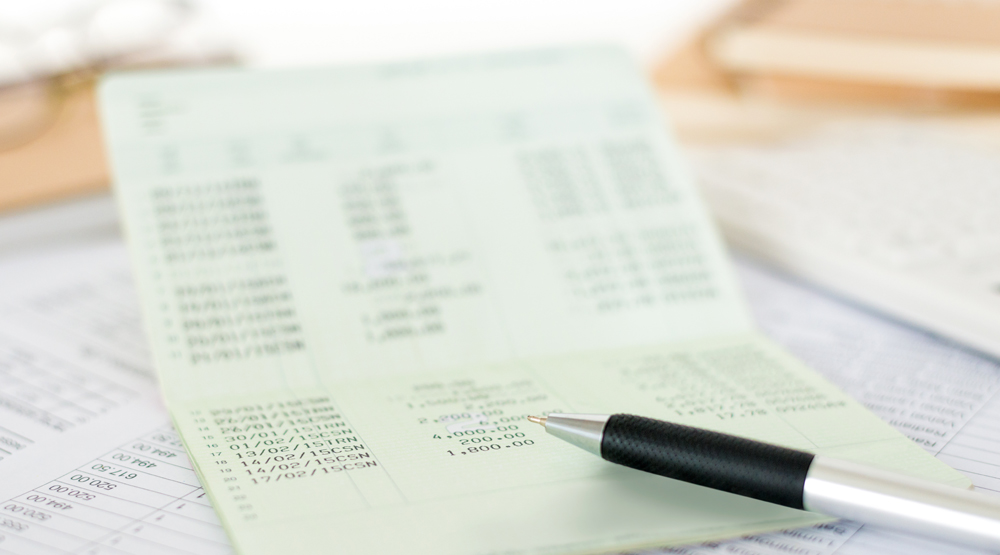
雇用保険の保険料は労働者の賃金の総額に保険料率を乗じて計算します。2023年現在の雇用保険の保険料は一部の業種を除いて1.55%。労働者負担が0.6%で、事業主負担が9.5%となっています。
上記は基本的な保険料の計算式です。また、失業保険の金額も賃金をベースにして計算されます。海外で勤務する場合、国内で賃金が発生しているかどうかによって扱いが変わるため注意が必要です。
国内給与が発生する場合
国内で給与が発生する場合は、国内で勤務する場合に通常支払われるべき給与の額を雇用保険法上の賃金と解釈して保険料を算定します。
たとえば海外手当や在外手当などは国内で就業していれば発生しません。そのため保険料算定上の賃金には含めることなく計算することになります。失業給付を受けるときの算定基礎額としてもこの時の賃金が使われます。
国内給与が発生しない場合
在籍しながら海外赴任した場合でも、出向先で賃金がすべて支払われて国内では給与が発生しない場合もあります。国内の企業に籍はあるので雇用保険の被保険者資格は継続するものの、賃金が発生していないことになるため、失業給付を受ける場合には注意が必要になります。
つまり、失業給付の計算対象となる給与がないため、失業給付の1日当たりの金額を計算することができなくなってしまうのです。
参考サイト:厚生労働省「雇用保険料率について」
海外赴任後の自己都合退職による失業給付
自己都合退職の場合の例を見てみましょう。たとえば赴任期間が1年以上あって帰国してから1年以内に自己都合退職をしたとします。そうすると、被保険者期間として必要な期間が足りず、失業給付が受けられない可能性があります。
失業保険給付の条件
自己都合で退職した人が失業保険の給付を受けるためには、「離職前の2年間で通算12か月以上の被保険者期間」が必要です。つまり、1年以上海外赴任している場合には、帰国してから1年以上の被保険者期間がないと失業給付を受けられないのです。
受給期間延長の申請
海外赴任のため、日本で30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合には、この失業保険の算定対象期間を4年間まで延長することが可能です。通常の受給給付期間である1年間と、延長期間の3年間をプラスし、離職日の翌日から合計4年間が最長となります。
これは海外赴任に限ったルールではなく、妊娠や出産・介護等の理由で働けない場合も同様です。また、海外赴任が決まった当事者だけではなく、帯同するために仕事を退職する配偶者にも当てはまります。そのため、配偶者が帰国してから再就職を考えている場合や、赴任期間が決まっていない場合には延長の手続きを行っておくのがオススメです。
なお、雇用保険の1日当たりの基本手当は「基本手当日額」に基づいて決まります。基本手当日額とは、離職日の直前6カ月間の賃金総額を180で割り、その金額に5段階に分かれる給付率を掛けて算出されます。
ただし、海外勤務期間中の賃金が著しく低いと認められる場合には、例外的に海外勤務前の給与を元にして失業給付の金額を算定することもあります。帰国後まもなく退職する場合は、この期間の延長を利用するようにしましょう。
海外赴任における労働保険とは
労働保険とは、雇用保険と労災保険(労働者災害補償保険)の総称です。
雇用保険は前述のように、失業や出産などのリスクに対して、失業手当や雇用調整助成金などの給付を行い、生活や雇用の安定を図ることが目的です。雇用形態にかかわらず、条件を満たした場合に加入し、その保険料は事業主と労働者で負担します。
一方の労災保険は、業務または通勤の事故による病気や怪我、障害、または死亡した場合に補償をする制度です。労働災害や通勤災害、死亡による遺族の生活保障などの給付があり、労働者の安全や遺族の生活を守り、労働者を保護することが目的です。会社自体に加入が義務付けられており、労災保険の保険料は全額雇用主が負担します。
労災保険の適用
海外勤務中に労働災害が起きた場合はどうなるのでしょうか。それは、「出張」なのか「派遣」なのかによって、適用が受けられるかどうかが異なります。海外出張の場合は、国内での災害と同様に扱われ、労災保険が適用されます。
しかし、海外派遣の場合には、「特別加入」をしていない限り、日本の労働保険は適用されません。基本的には、派遣先の国の災害補償制度の適用を受けることになります。その理由は、労働災害補償保険法が属地主義*の考え方を採用しているため、日本国内においてのみ効力を発揮することからです。
*属地主義とは、「法律の適用範囲をその国の領域に限定し、その効力は外国には及ばない」という考え方のこと。
労災保険における海外出張
海外出張とは、日本にある会社などの本社や支社などから、一時的に海外の支店や現地法人などに赴き、業務を行うことです。出張期間は数日から数週間程度が一般的であり、出張先での生活費や交通費は会社が負担します。
労災保険における海外派遣
海外派遣とは、日本から自社の従業員を海外の現地法人や支店などに長期間派遣することで、転勤や出向は「海外派遣」に該当します。派遣期間は数か月から数年に渡ることが多く、現地での生活費や住居費、交通費などは派遣された従業員自身が負担することがほとんどです。
つまり、海外出張は市場調査や商談などの一時的な業務を行うための渡航であり、海外派遣は会社の事業展開や現地での人材育成のために派遣されることを指します。ただし、出張と派遣の違いは渡航期間ではなく、国内の事業場が指揮命令を出しているのか、海外の事業場指揮命令を出しているのかで判断されることに注意してください。
もし、どちらに当てはまるのかがわからない場合は、労働基準監督署に確認してみましょう。
特別加入制度とは
通常、労災保険の適用範囲は日本国内のみですが、一定の要件を満たした場合に限り加入を認めています。海外派遣者だけの制度ではなく、一人親の方やフリーランスなどの労働者以外が対象です。
海外派遣者は、現地の労災保険制度が日本に比べて補償内容が充実していなかったり、制度自体がなかったりする場合もあります。そのため、日本の労災保険と同じ水準の補償を受けられるようにしたものが「特別加入制度」です。加入は任意ですが、遡って加入をすることはできないため、海外赴任が決まったら早めに手続きをするといいでしょう。
労働保険は、健康保険や厚生年金保険などの「社会保険」と一体的に提供される保険です。職場でのリスクに備えることは、労働者にとって大きな安心材料となります。とくに海外赴任など労働環境が大きく変わる場合には、現地で困ることがないように、事前によく調べておくようにしてください。
まとめ
海外進出する際は、海外赴任となる人材の選出や生活のサポートも必要になります。海外赴任特有の問題として挙げられるのがビザの取得や社会保険などの処理です。また帯同家族に対するフォローも必要になります。
雇用保険に限らず、社会保険はそれぞれ赴任するときの形態や赴任先の国によって違いがあります。ここで紹介しているのは基本的な対応です。それぞれの国やパターンに応じて個別に判断と対応が必要です。