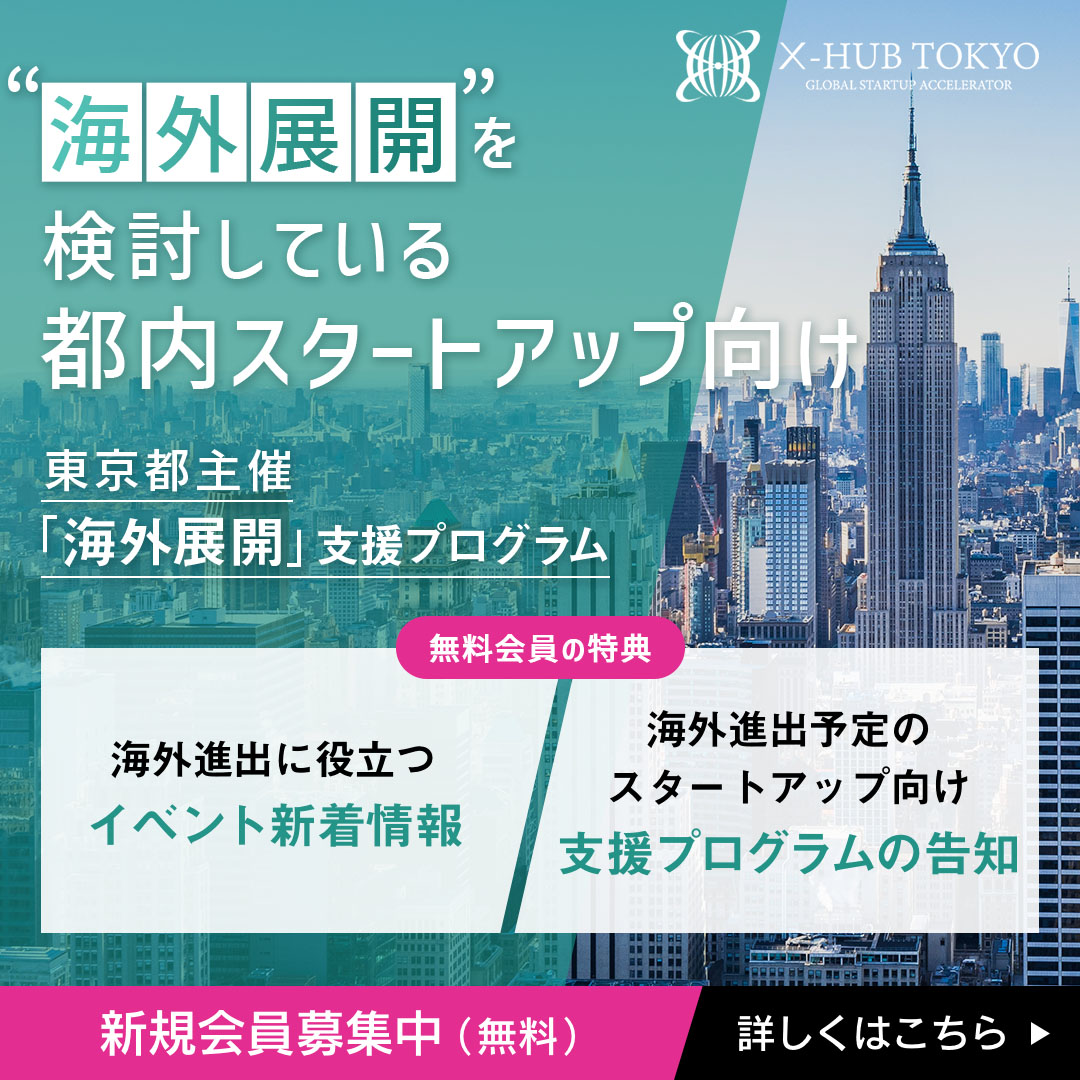世界のEC(電子商取引)市場は、近年急速な拡大を続けています。消費者の購買行動がオンラインにシフトする中で、企業の成長戦略においてECは不可欠な要素となりました。スマートフォンやデジタル決済の普及により、消費者が日常的にオンラインで商品やサービスを購入する環境が整い、世界各地で新しいビジネスモデルが定着しつつあります。
本記事では、世界および日本のEC市場規模の現状と成長要因、主要国との比較、そして越境ECの可能性について解説します。
世界のEC市場規模と成長要因
世界のEC市場は、なぜこれほどまでに拡大を続けているのでしょうか。その規模と成長をけん引する要因を掘り下げていきます。
世界全体の市場規模の推移
国際機関や調査会社の報告によると、世界のBtoC EC市場規模は2023年に約5.47兆米ドルに達しました。今後も高い成長が見込まれ、2030年には約17.77兆米ドルに拡大すると予測されています(年平均成長率:約19.1%)。これは世界全体の小売市場に占める割合が一層高まることを意味し、従来の店舗中心の販売からオンラインへのシフトが加速していることを示しています。特にアジア太平洋地域は2023年時点で世界市場の約58%を占め、グローバルなECの中心地として存在感を増しています。
成長をけん引する要因
EC市場の拡大を支える背景には、いくつかの要因があります。第一に、スマートフォンの普及により、インターネット接続環境が世界的に整ったことが挙げられます。加えて、SNSを活用したマーケティングやインフルエンサーによる販売促進が購買を後押しし、消費者の購買行動を変化させています。
さらに、コロナ禍を契機に非対面での購買行動が一気に広がり、その後も利便性が評価され定着しました。物流や決済システムの整備も進み、EC利用の障壁が下がったことも成長を後押ししています。
定着したEC形態と新たな成長分野
すでに主要国では、モバイルコマースが一般化しており、オンライン取引全体の過半数を占めるケースも珍しくありません。また、サブスクリプション型サービスも音楽や映像配信にとどまらず、食品や日用品といった分野に広がり、消費者に定着しています。
一方で、次なる成長分野として注目されるのがライブコマースやAIを活用したパーソナライズ型ECです。中国を中心に大規模市場が形成されつつあるライブコマースは、双方向性を持った購買体験として新たな価値を提供しています。世界のライブコマース市場は2024年に約1,284億米ドル、2033年には約2.47兆米ドルに拡大すると見込まれており、成長ポテンシャルの大きさがうかがえます。
パーソナライズ型ECは、AIやビッグデータを活用し、消費者一人ひとりの購買履歴や閲覧行動に基づいた商品提案を行う仕組みです。ファッションや化粧品、食品の定期購入サービスなどで活用が広がっており、AmazonやNetflixといった大手企業がレコメンド機能を高度化させています。また、東南アジアや中国のECプラットフォームでも導入が進み、既存サービスに追加機能として搭載されるケースが増えています。こうした動きは消費者の利便性を高めるとともに、事業者にとっては顧客ロイヤルティの向上や売上拡大にも直結するため、今後も注目が続くでしょう。
主要国・地域別のEC市場比較

続いて、世界最大の中国市場から、米国や欧州、そして新興国の市場まで、主要な国・地域別のEC市場を比較します。
中国は世界最大のEC市場
中国は世界最大のEC市場として、他国を大きく引き離しています。アリババや京東(JD.com)といった大手プラットフォームに加え、近年はDouyin(中国国内版TikTok)のEC機能が台頭し、新しい消費スタイルをけん引しています。モバイル決済の普及率が極めて高く、現金を使わない購買行動が一般化している点も特徴です。さらに、地方都市や農村部に至るまで物流網が整備され、全国規模でECの利便性が浸透しています。
特筆すべきは、ライブコマース市場の急成長です。動画配信プラットフォームであるTaobao Live(タオバオライブ)やDouyin、Kuaishouなどを通じて行われるライブ配信型販売は、エンターテインメントと購買を融合させた新しい形態として急速に普及しました。2023年にはライブコマースが中国EC全体の約31.9%を占める規模にまで成長しており、人気インフルエンサーが1回の配信で数十億円規模の商品を販売する例も見られます。視聴者がリアルタイムで質問や購入を行える仕組みと、モバイル決済の普及が相まって、この分野の市場を爆発的に拡大させました。
米国と欧州の市場動向
米国ではAmazonが圧倒的な存在感を持ち、国内EC市場の約40%のシェアを維持しています。豊富な商品ラインナップと迅速な配送網が強みであり、サブスクリプションサービス「Amazon Prime」の浸透も市場拡大に寄与しています。さらに、近年は中小企業や個人事業者がShopifyなどのプラットフォームを通じて直接消費者に販売するケースが増加し、競争が一段と活発化しています。
欧州でもEC市場規模の拡大が続き、特にドイツとイギリスが二大市場として成長をけん引しています。ドイツは安定した購買力と堅実な消費行動が特徴で、イギリスではファッションや食品のオンライン購入が広く浸透しています。一方で、南欧や東欧ではEC化率がまだ低く、今後の成長余地が大きい地域といえます。
EUは加盟国間でモノやサービス、人、資本の移動を自由化した「単一市場」を形成しており、企業は一度EU域内で販売体制を整えれば、他の加盟国にも比較的スムーズに展開できる可能性があります。ただし、消費者の嗜好や税制、商習慣は国ごとに異なるため、共通基盤と現地対応を組み合わせた戦略が求められます。
新興市場の台頭(東南アジア・インド・中東・アフリカなど)
新興市場の中でも注目を集めるのが東南アジアです。スマートフォンの普及によるインターネット接続環境の整備と中間層の拡大を背景に、ShopeeやLazadaといったプラットフォームが急成長を遂げています。同地域のEC市場は2024年時点で約1,840億米ドルに達しており、2030年には約4,100億米ドルへ倍増すると予測されています。
インドも人口増加とスマホ利用の拡大を背景に、巨大な潜在市場とされています。2024年時点で約1,077億米ドルの市場規模に達し、2033年までには6,504億米ドル規模に拡大する見込みです。
さらに、中東では高所得層を中心としたオンライン購買が増加しており、国際的な企業にとって魅力的な市場となっています。特にサウジアラビアやUAEを中心に、中東およびアフリカ全体では2025年には約1,000億米ドル規模に拡大すると見込まれています。
日本のEC市場と越境ECの可能性

拡大を続ける世界のEC市場に対し、日本の現状はどうなっているのでしょうか。ここでは、日本の市場動向とともに、越境ECの可能性について解説します。
日本のEC市場規模と特徴
経済産業省の調査によると、2024年の日本のBtoC EC市場規模は約26兆円、そのうち物販系は15兆2,194億円に達しました。年々拡大が続く一方で、小売市場に占めるEC化率は9.78%にとどまり、2023年時点の中国(29.7%)や英国(26.5%)、世界平均(19.0%)と比べても依然として低い水準にあります。
国内では食品、日用品、ファッションなど幅広い分野でEC利用が浸透しているものの、物流コストの上昇や人手不足といった課題も抱えています。
越境ECの拡大と実務上の留意点
こうした環境下で注目が高まっているのが、日本から海外へ製品を販売する越境ECです。世界の越境EC市場は2024年に1.01兆米ドル、2034年には6.72兆米ドルへ拡大し、2025年から2034年の年平均成長率は約23.1%と推計されています。この大幅な成長は、今後のビジネスチャンスの広がりを示唆しています。
日本製の化粧品、食品、ベビー用品は品質への信頼性から海外でも高い評価を得ており、特に中国や東南アジアで根強い需要があります。さらに、インバウンド需要との相乗効果により、一度訪日した消費者が帰国後に日本製品をオンラインで購入するケースも増えています。
越境ECを展開する際は、まず市場調査を行い、現地の需要や消費者嗜好を把握することが重要です。そのうえで、国際配送ルートの設計や配送コストの最適化、現地通貨・電子決済への対応、輸出入に関する法規制の順守、カスタマーサポート体制の整備など、幅広い実務対応が求められます。現地パートナーとの連携や各種支援制度を活用することで、よりスムーズな展開が可能となるでしょう。
まとめ
世界のEC市場は今後も拡大が続き、日本企業にとっても大きなビジネスチャンスを提供しています。モバイルコマースやサブスクリプションはすでに定着した一方で、ライブコマースやAIを活用した新しい販売手法には成長余地が残されています。海外市場では国や地域ごとに市場環境や規制が異なるため、最新の情報収集と柔軟な戦略立案が成功の鍵を握ります。特に越境ECは、自社の強みを活かしながら新しい顧客層にアプローチできる有力な手段として注目されており、今後の事業展開において重要な選択肢となるでしょう。
こうした成長市場への参入を目指す企業を支援するため、東京都では「X-HUB TOKYO」事業を通じて、都内スタートアップの海外進出を後押しする多彩なプログラムを展開しています。海外展開に必要な知識や情報提供に加え、現地VCや大企業とのネットワーク構築、ピッチトレーニングやメンタリング支援など、企業のグローバル展開を幅広く支援しています。詳しい情報や最新イベントについては、ぜひ「X-HUB TOKYO」の公式サイトをご覧ください。