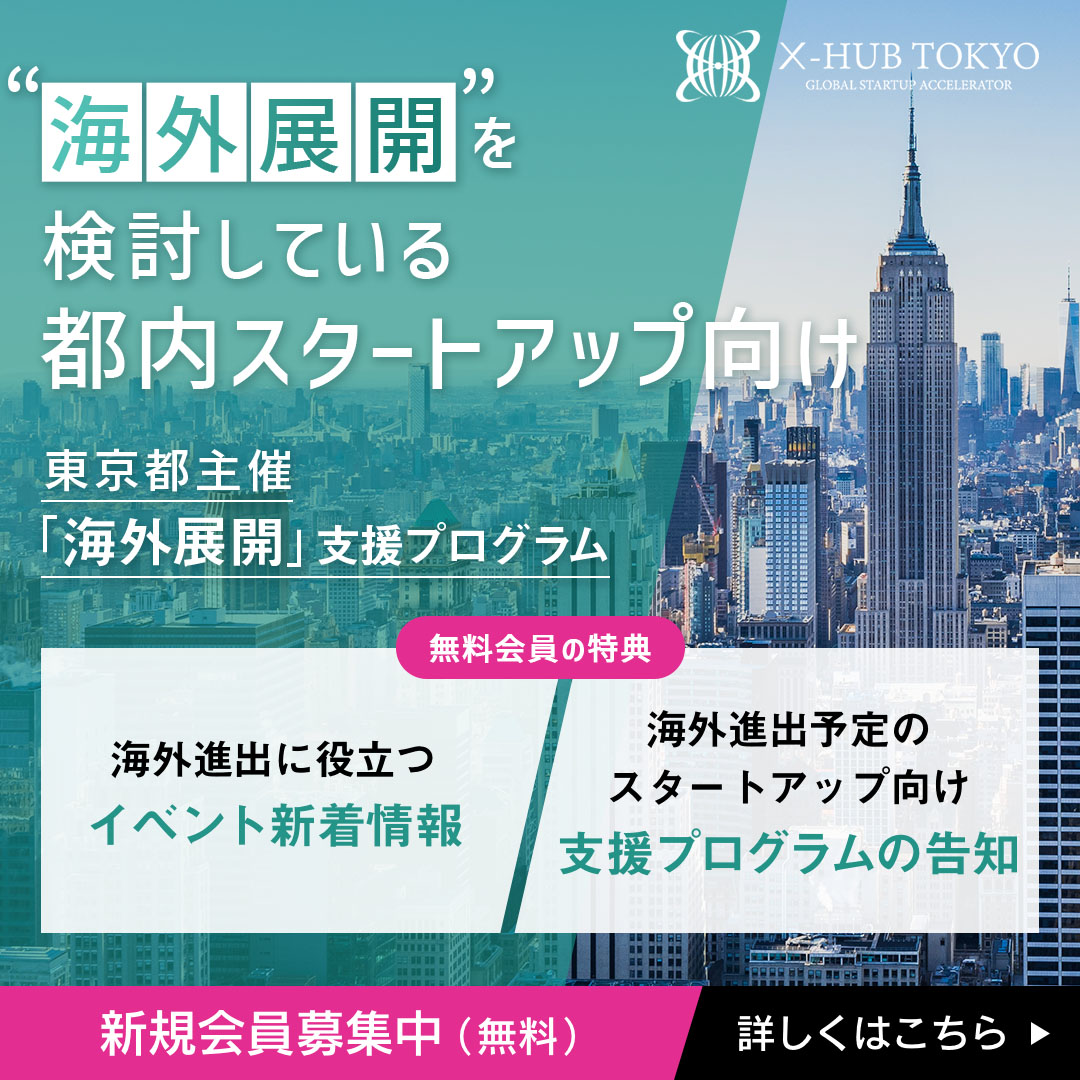世界で第4位約2.7億人の人口を有するインドネシアは、赤道にまたがる約14,000の大小さまざまな島々から構成されています。インフラ整備も進み、投資環境も整いつつあります。インドネシア経済が安定して発展を継続することができた理由、そして今後さらなる発展のための課題について調べました。
目次
インドネシアの堅調な成長を支えてきた「内需」
インドネシアは世界的に見ても堅調な成長を維持し続けている国です。2000年以降、経済成長率がマイナスになったことは一度もなく、2010年前後は6%台の成長率を記録しました。これは、主要産業である一次産品の価格が高水準だったことも要因の一つですが、近年はコモディティ価格*の下落により成長率は鈍化しています。
世界の主要な新興国は、2000年に入ってから経済成長率に陰りが見え始めました。タイを中心に始まった「アジア通貨危機」によりアジア各国がマイナス成長に陥った1998年を除けば、インドネシアは長期にわたり安定した成長を遂げてきた数少ない国と言えるでしょう。
では、インドネシアが世界不況の中でも高い成長率を維持できた理由は何でしょうか。それは、輸出依存度が低く、旺盛な個人消費が経済成長をけん引する「内需主導型経済」であることです。2008年のリーマンショックで世界各国が大きな打撃を受ける中でも、インドネシア経済は4%台の成長を保ちました。
*コモディティ価格とは、商品先物市場で取引される「原油や天然ガス・ガソリンなどのエネルギー」「金・銀・プラチナなどの貴金属」「小麦・大豆・とうもろこしなどの穀物」これらの価格のことを指します。この市場の動向は先進国の景気や為替市場にも影響を及ぼすため、注目度の高い項目となっています。
消費市場が拡大した理由と交通渋滞問題
インドネシアの消費市場が拡大した背景には、主に2つの要因が挙げられます。
雇用の拡大
まず、製造業やサービス業の発展に伴い雇用が拡大しています。インドネシアの対内直接投資受入額はこの10年間で急増しており、それが自動車や日用品などの内需の投資拡大につながり、製造業が活況となったと考えられます。
もともと2008年~2009年は世界金融危機で多くの国が不況に陥りました。その一方で内需主導の成長が堅調で、政治的にも安定していたインドネシアは有望な投資国として世界で注目を集めたのです。
産業の高度化
またインドネシアが発展することで、産業構造にも変化があらわれました。農林水産業の比率が低下して、逆に製造業・サービス業の比率が増加しています。いわゆる産業の高度化が進み所得水準が上昇したことで、貧困層が減少しインドネシアの消費市場拡大につながっています。
このように産業構造が変わっていくと、農村から都市とその近郊へと人口も移動していきます。インドネシアはスマトラ島やジャワ島、ニューギニア島などからなる列島国家です。この中で経済的な中心地とされているのがジャワ島西部のジャカルタ首都圏。ジャカルタは、オランダによる東インド支配の時代から政治の中心地として機能してきました。
都市へ集中する人口
ジャカルタの人口は2023年には1,133万人、首都圏も含めれば約3,400万人が暮らしています。そんな首都ジャカルタでは、世界最悪とも言われる交通渋滞が深刻化しています。2018年の交通渋滞による経済損失は百兆ルピア(約7,775億円)、国家予算の5%にも及ぶと言われていました。
これは道路自体が少ないことに加え、自動車やバイクの保有台数の増加や市内を移動ができる公共交通機関がなかったことが原因です。日本政府と日本企業が全面支援した大量高速鉄道「MRT南北線」が2019年に開業し、現在は第2フェーズの建設中です。まだ渋滞を緩和するまでにはいたっていないものの、東西線も日本の技術を活用して建設されることが決まりました。2031年の完成を目指し、巨大プロジェクトが動き出しています。
インドネシアの個人消費は世界から注目の「巨大市場」

インドネシアの個人消費は、若く豊富な労働力によって支えられ、ASEAN内でも注目の「巨大市場」となっています。
個人消費の拡大
新型コロナウイルス流行前のインドネシアのGDP、その約6割を占めたのは民間消費です。インドネシアは世界で第4位の人口を抱え、人口増加や最低賃金の上昇などを背景に、安定した推移を見せてきました。
新型コロナウイルスの感染拡大により一時は二輪車販売なども落ち込みが見られましたが、半導体不足など部品の供給は大幅に改善しました。インドネシア二輪車製造業者協会によると2023年通年では623万6992台が販売され、市民の必需品である二輪車市場は大きなマーケットになっています。
また、国民の生活水準の向上とともに消費も多様化し、日用品や通信関連の消費が増加していることも個人消費の拡大に寄与しています。インドネシアの2023年の1人当たりGDPは4,919USドル(世界116位)で、ASEAN内で比較すると例えばフィリピン(3,906USドル、126位)より高い一方、マレーシア(12,090USドル、72位)との差は大きい状況です。
しかし、今後1人当たりGDPが5,000ドル台、10,000ドル台まで上昇すれば、耐久消費財の普及など個人消費もさらに押し上げられることになるでしょう。
安定した消費は平均年齢の低さから
インドネシアは年齢構成が若く労働人口が多いことから、今度も成長が期待できる開拓余地が大きい市場として注目されています。2024年の労働人口は1億4,938万人と、総人口の半分を超えた53.60%を占めています。2030年に生産年齢人口のピークを迎え、2040年頃まで増加が続くだろうと予測されています。
中間層が拡大することは、安定した消費を促進する要因にもつながります。車・住宅・教育など、高額な買い物やサービスを利用するため、個人ローン、投資サービス、保険など金融サービスに対する需要が増加し、ファイナンス業界の発展も期待されています。この巨大な消費市場に対し、日本企業が参入する動きも加速しています。これから海外進出を考えている企業にとっても大きく期待できる市場であるといえるでしょう。
出典:
外務省「海外進出日系企業拠点数調査」
国際通貨基金(IMF)「WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASES」
インドネシア経済の強みと課題
人口ボーナスが経済を後押し
インドネシア経済の強みは、人口ボーナスによる消費の活発化にあります。1980年に約1億4,700万人であった人口が、2024年3月現在では2億7,870万人を超えています。これは中国、インド、アメリカに次ぐ規模です。経済成長の続くインドネシアでは、依然出生率が高く、2030年代には3億人を突破し、2045年頃まで増加が続くと予想されています。
さらに、生産年齢人口の割合がそれ以外の人口の2倍以上である「人口ボーナス」と呼ばれる状態が経済成長を後押ししています。子どもと高齢者の割合が少ないことによって教育費や医療費が抑えられることで、個人消費が活発になり、経済規模が拡大しやすい状況にあるのです。
貧富の格差が課題
一方で、インドネシアでは貧富の格差をなくすことが大きな課題です。2023年3月の貧困率は9.36%と、新型コロナウイルス流行以降では最低の数字となりましたが、流行前の水準には未だ回復していません。とくに農村部の貧困率が高く、都市部や観光地では低い傾向にあり、農村部と都市部には大きな差があるといえるでしょう。
インドネシアは日本と同じ合計9年間の義務教育期間を定めていますが、施設や設備・教師の質など地域の格差がまだまだ大きいです。農村部では学校までの距離が遠く、通学自体が困難である場合も多く、経済的な負担の問題もあります。教育水準の低さは雇用機会を制限することにつながるため、農村部はどんどん取り残されることになってしまいます。反対に、都市部の生活水準は高く、物やサービスの価格も年々上昇し、富裕層も増加しています。相続税のないインドネシアでは、さらに貧富の差が広がる可能性もあります。
ジョコ前大統領は、国民的なバイク・タクシー配車アプリ「Gojek(ゴジェック)」の共同創業者ナディム・マカリム氏を教育文化大臣に迎え、技術革新や教育水準の向上を進めました。インドネシア政府は、貧困世帯を対象とした食料支援や現金給付など貧困削減に取り組んでいますが、急激な経済成長によって広がる格差をどう埋めていくかが今後の課題です。
ジョコ前政権が行った経済政策
ジョコ・ウィドド前大統領は2014年10月20日から2024年10月20日まで、10年間にわたり大統領を務めました。
外資誘致政策
ジョコ前政権は経済成長の底上げを狙い、日本企業を含む外資の融資を推進するために、以下のような項目を主要政策に盛り込みました。
- インフラ開発
- 投資促進(規制緩和の推進や法整備)
- 人材開発(品質管理や労働生産性の向上)
投資促進や雇用機会の創出を目的とし、2020年11月にはオムニバス法(雇用創出法)が制定・施行されました。オムニバス法を巡っては違憲判決や代行政令の制定、オムニバス法の改正などが続いていますが、最低賃金や解雇規定・退職金規定の改善が見込まれ、日本企業の参入促進が期待されます。
また人材開発においては、技術革新やインフラ整備の遅れ、労働者のスキル不足により、インドネシアの労働生産性はASEAN諸国の中でも低い水準にあります。そのため、どうしても人件費が割高に感じてしまい、人件費に見合った生産性の向上や現場力強化がインドネシアの課題であるともいえるのです。
首都機能移転
現在ジャカルタ首都圏の人口は急激に増加し、ジャカルタの所得水準は地方の数倍あります。政治と経済の中心地であるジャカルタが消費の中核を担っているのが現状です。そこで2019年の8月インドネシア政府は首都をジャカルタからカリマンタン島・東カリマンタン州の東部に移転する方針を決定しました。
首都機能を移転することでジャカルタへの一極集中をなくし、首都圏と地方の格差を是正する目的です。首都移転計画はコロナ対応を最優先とし一時はストップしていましたが、2045年までの完了を目指し進められています。2024年8月には新首都予定地で独立記念日の式典が開かれ、今後は公務員の移住や政府機関の移転などが進められる予定です。
ただし、総工費は少なくとも日本円でおよそ4兆4000億円にのぼり、その8割を民間と海外からの投資から賄うとし、資金調達は難航しています。さらに新しい首都はジャングルを切り開いて建設されることから、森林破壊や環境汚染などの声も上がっており、ジャカルタからの首都移転に向けてどのように進むのか今後の動向が注目されています。
プラボウォ新政権の公約と課題
2024年2月の大統領選でプラボウォ国防相が勝利し、10月にプラボウォ新政権が発足、副大統領にはジョコ前大統領の長男ギブラン氏が選出されました。新政権では、スリ=ムルヤニ財務相をはじめ、重要閣僚を中心に前政権から留任・再任しています。
重要閣僚の留任によって政権運営の安定や政策の継続性を示していますが、大臣や副大臣などのポストが大幅に増加したことにより、効率的な政策運営が課題となっています。汚職対策の強化、地方分権化の推進と中央政府との関係調整も必要になるでしょう。プラボウォ氏はジョコ前政権の路線を踏襲する一方、さまざまな公約や任期中の成長率の大幅引き上げを掲げており、財政運営の行方が注目されています。
新政権の公約
プラボウォ新政権は、任期中に経済成長率を平均8%まで引き上げるという目標を掲げています。これはジョコ前政権下の平均4%からの倍増となり、達成には多くの障壁が考えられます。産業構造の改革や生産性の向上、イノベーションの促進や人的資本への投資が不可欠ですが、どれも長期的な視点で継続的な政策の実行が必要です。
新興国であるインドネシアにとって、財政の健全化を維持することは国際金融市場からの信頼確保に欠かせません。効率的な資金配分や汚職防止のための統治体制の強化も必要になるでしょう。新政権は、ジョコ前政権から引き継いだ首都移転計画の継続も表明していますが、巨額の資金調達や環境保護団体からの批判、現地住民との土地問題などこちらも多くの課題に直面しています。
産業構造のさらなる変革
近年、インドネシア経済は資源輸出に依存する構造からの脱却を目指し、経済の多角化を進めています。高付加価値産業の創出やデジタル経済の推進、製造業の高度化やIT産業の育成、サービス産業の拡大などが挙げられます。また、グリーン経済への移行も課題であり、再生可能エネルギーの導入や電気自動車産業の育成、持続性の高い農業の推進が必要となるでしょう。
これらの実現には、教育システムの改革や技術革新の促進に加え、外国直接投資の誘致が不可欠です。ルピア相場の安定性強化に加え、インフレ圧力の管理や対外債務の管理など、多くの課題を克服する必要があります。新政権の政策実行力や産業構造の改革が、今後の経済発展を左右するでしょう。
まとめ
インドネシアは約2.7億人の人口を有し、個人消費が旺盛で消費市場としての潜在力の高い国です。ASEAN最大の経済規模と高い成長ポテンシャルを持ち、新政権の政策実行力や産業構造の改革が、今後の経済発展を左右するでしょう。インドネシアの成長はASEAN全体、アジア太平洋地域にも影響を与える可能性があり、国際社会からも注目されています。
都内スタートアップの海外進出を支援する「X-HUB TOKYO」では、インドネシア進出を目指す企業へ向けたプログラムを提供しています。海外進出・海外展開に関する情報発信に加え、実例を踏まえたアドバイスやサポート、海外進出に役立つイベントも随時開催しています。海外進出を検討中の方はぜひ最新のイベント情報をチェックしてみてください。