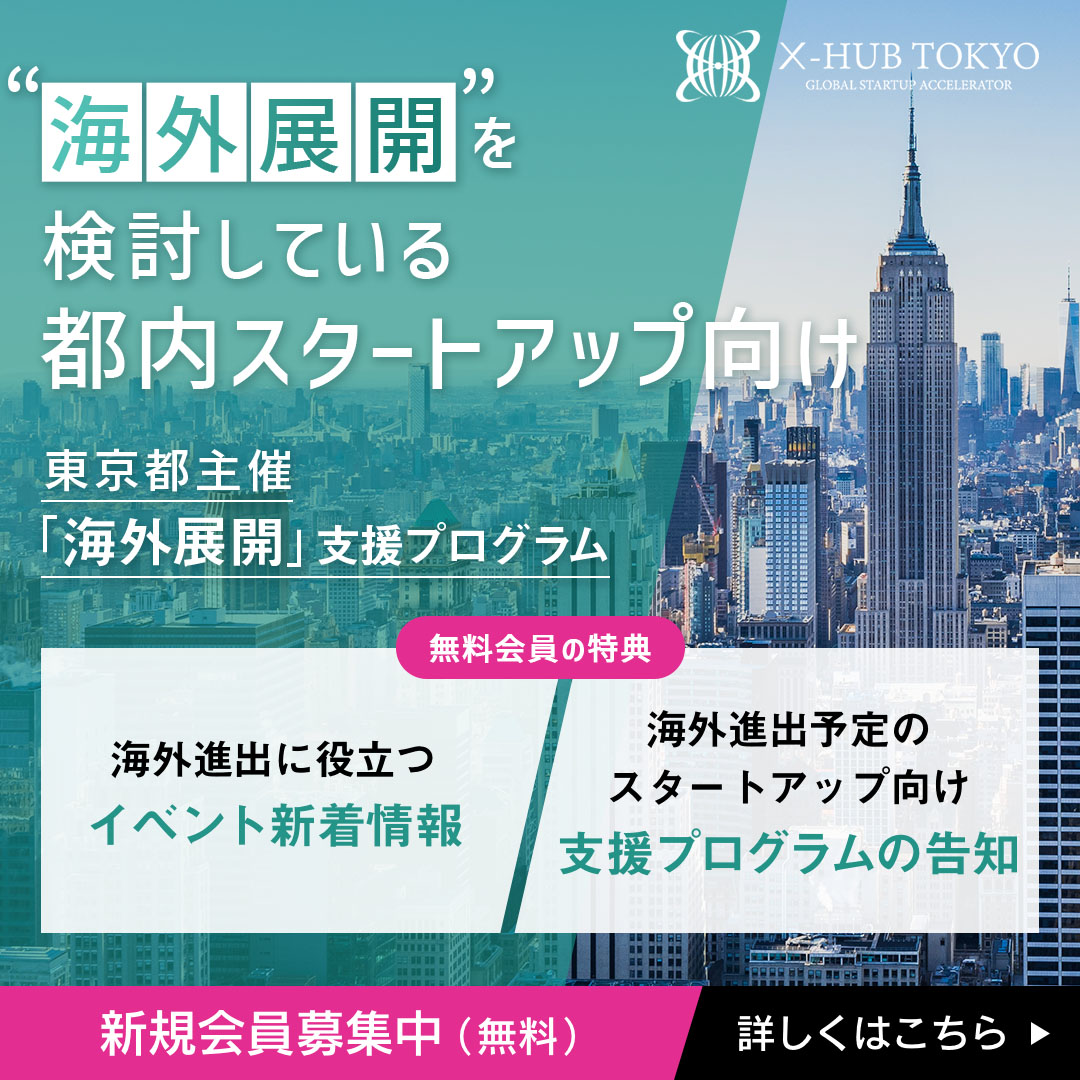安価で優秀な労働力を抱えた国としてベトナムは世界の外資企業から投資を集めてきました。しかし、ベトナム経済はその変遷から生まれた課題にも直面しています。ベトナム経済が抱える課題と今後の動向についてまとめました。
経済発展の鍵は「ドイモイ政策」
ベトナムの正式名称は「ベトナム社会主義共和国」。2023年に人口が1億人を超え、急激な経済成長を続けています。ベトナム戦争終結後の1976年、南北統一により社会主義体制が確立されました。国民の平等な暮らしを目指しましたが、東欧諸国からの援助が徐々に削減されたことで、制度の維持が難しくなっていきました。
この状況を打開するため、南北統一から10年後の1986年に「ドイモイ政策」が導入されました。“ドイモイ(Doi Moi)”とはこの時に提唱されたスローガンで、「刷新」を意味しています。ドイモイ政策では、社会主義体制を維持しながら市場経済を導入するという大きな方向転換が行われました。この政策転換により、配給制の生活から「お金でものが変える経済」へと移行し、ベトナム経済に活気をもたらしたのです。
ドイモイ政策の成果
ドイモイ政策により、ベトナムは急速な経済成長を達成します。これまで禁止されていた個人営業が奨励され、私企業や私有財産が認められるようになりました。徐々に生活が豊かになることで国民の意識も大きく変わり、勤労意欲が増し、生活水準が大きく向上しました。
農業部門の改革も進め、生産性向上と農村部の発展を促進しました。同時に、製造業も拡大し、国内産業の多様性が増した結果、ベトナム製品の国際競争力が強化され、輸出産業が大きく成長しました。
また、社会主義政策の緩和を実施したことで大きく変わったのが、1995年のASEAN加盟 です。国際社会への貢献をかかげ社会主義政策を緩和したことで、ASEANの一員となることができました。ベトナムは以降、自由貿易協定の締結や国際経済組織への参加を通じて、経済のグローバルな結びつきを強化しています。
さらに海外からの直接投資を積極的に受け入れ、対外開放政策を推進しました。1988年には外国投資法を公布し、外国資本の企業がベトナムで活動できるようになりました。外国企業との協力による技術移転や生産性の向上、貿易の拡大により、ベトナムの製品やサービスは世界市場で品質とコストの両面で競争力を持つようになったのです。
ベトナム通貨ドンの変動と為替介入問題
 2000年代のベトナムは、工業化の進展により経済構造が大きく変化し、計画経済から市場経済へのシフトも実現しました。ベトナム経済の成長を支える原動力となったのが海外からの投資です。
2000年代のベトナムは、工業化の進展により経済構造が大きく変化し、計画経済から市場経済へのシフトも実現しました。ベトナム経済の成長を支える原動力となったのが海外からの投資です。
ドンの変動と経済への影響
輸出競争力維持を目的とした戦略的な政策の一環として、ベトナムはドンの価値を意図的に下落させました。 1987年初頭に1USドル=22.9ドンだった為替相場は、2024年12月現在25,404ドン前後まで下落しています。この大幅な下落は、短期的に輸出競争力を高める効果をもたらしましたが、通貨の信用力低下や輸入コストの上昇、金融政策の運営が困難になるといった長期的な課題も存在します。
ドンの価値が不安定になると、投資家や企業のベトナム経済への信頼が損なわれ、投資抑制につながる可能性があります。さらに、インフレやデフレーションといった問題を引き起こし、中央銀行による適切な金融政策の実行を困難にするリスクも高まります。
ドン安政策はベトナム経済の成長をけん引しましたが、過度な変動は企業の経営や投資家心理に悪影響を及ぼすため、通貨の安定化が求められています。ベトナム政府は、経済成長の維持とドンの安定化を両立させるための政策を策定していく必要があるでしょう。
為替介入問題
2020年12月にアメリカ財務省は為替報告書の中で、ベトナムを「為替操作国*」として認定しました。為替操作とは、政府や中央銀行が、自国通貨の価値を意図的に操作し、貿易収支や経済状況を改善しようとする行為です。ベトナムは、アメリカとの関係悪化を避けるため、為替政策の見直しを迫られています。
為替介入は、外国為替相場の急激な変動を抑え、その安定化を図ることを目的としますが、必ずしも自国通貨の価値を操作する目的とは限りません。ベトナムの中央銀行は、2021年2月に為替介入の頻度を減らすとの声明を出しましたが、その後もアメリカの監視は続いています。
2021年4月以降のアメリカ財務省の報告書では、ベトナムは3つの基準を満たしていたものの、ベトナム政府との問題解決に向けた協議に満足していることなどを理由に、「為替操作国」からは外されました。 しかし、状況を注視する必要があるとして、「監視対象国」へ指定されました。
2024年11月の報告書では、ベトナムは経常収支黒字と対米貿易黒字の2項目が該当し、引き続き「監視対象国」に指定されています。これは、ベトナム経済の成長に伴い、対米貿易黒字が拡大し続けていることが主な要因と考えられます。
*「為替操作国」とは、対米通商において優位な立場をとるために外国為替相場を人為的に操作していると米国が認定した国のことを指します。これは「大幅な対米貿易黒字、対国内総生産(GDP)比の経常黒字、持続的かつ一方的な為替介入額」という、3つの基準から判定されています。半年に1度発表する外国為替報告書を通じて公表し、為替操作国に認定された国は、アメリカとの間で2国間協議が実施されるほか、認定された国が是正措置を講じなければ関税の引き上げなどの制裁を課せられることがあります。
国際社会への参入に伴う課題
ドイモイ政策以降、ベトナムの国営企業は国内経済の安定化に大きく貢献しました。しかし、2007年のWTO加盟を機に、国際社会との競争が激化する中で、新たな課題に直面しています。
国営企業への懸念
ベトナム経済の発展をけん引した存在として忘れてはならないのが、外資企業と民間企業です。しかし、もともと社会主義経済国であったベトナムには、国家が所有する多くの「国営企業」があります。資源関連や運輸、エネルギー、通信関連などの産業に属する国営企業は健全な財政状況を維持しているケースが多く、今後も成長が期待されています。
その一方で、国営企業の中には非効率な経営を行い、生産性や収益性が低い企業も少なくありません。政治的な要因や歴史的な経緯から、経営責任の不透明さ、不正や腐敗の発生しやすさなどの問題も指摘されています。これらの企業の維持に必要な政府の財政支出は国家財政に大きな負担をかけるだけでなく、民間企業との競争力を低下させ、経済全体の活性化を妨げる可能性があると懸念されています。
国営企業再編の遅れ
ベトナムは2007年に世界貿易機関(WTO)に加盟しており、その際に国営企業と民間企業の公正な競争条件の確保が義務付けられています。また環太平洋パートナーシップ(TPP)交渉でも、国営企業の撤廃や公平な条件での競争環境がテーマとして話し合われました。
市場経済にシフトした国ではあるものの、今も共産党一党独裁体制は変わっていません。共産党幹部の天下り先として国営企業が使われているなど、国営企業の抜本的な民営化は困難なのが実情です。国営企業の払い下げもおこなわれているものの進行は停滞しています。共産党の影響下で国営企業に対する政府の優遇策や不透明な規制が、外資企業の参入を阻む障壁となる可能性もあるでしょう。
ベトナムの持続的な成長に向けた課題
 ベトナムは安価な労働力と成長市場を背景に、多くの企業から注目を集め、目覚ましい経済成長を遂げました。一方で、持続的な成長を阻むいくつかの課題が存在します。
ベトナムは安価な労働力と成長市場を背景に、多くの企業から注目を集め、目覚ましい経済成長を遂げました。一方で、持続的な成長を阻むいくつかの課題が存在します。
インフラ整備の遅れ
一つ目の課題として、インフラの整備が挙げられます。ベトナムは市場経済化のために、インフラ整備によって外資を呼び込む戦略を選択してきました。日本をはじめとする各国からの政府開発援助(ODA)を活用しながら、道路、港湾、空港などの整備が進められてきました。
一方で、インフラ整備のための巨額な投資は、財政を圧迫し、公的債務残高が増加する要因となっています。財政赤字による対外借入額の累積は、健全な財政運営を脅かすとの懸念から、ベトナムは2012年に公的債務残高をGDPの65%以下に抑える目標を設定しました。その結果、公的債務残高が上限に近づきインフラ整備が停滞する事態も過去に発生しており、財政状況の健全化とインフラ整備の両立が課題となっています。
ベトナムでは、大都市間を結ぶ交通網の脆弱性が指摘され続けています。トラック輸送は慢性的な渋滞に悩まされ、鉄道網も老朽化が進んでいます。ベトナム政府はインフラ整備を最優先課題としていますが、実現の時期は依然として不透明な状況です。
電力不足の長期化
二つ目の課題は、電力不足です。ベトナムは経済成長に伴う電力需要の増加により、深刻な電力不足に直面しています。主な原因は、国際的な石炭価格の高騰と、国内の石炭生産量の減少です。石炭価格の高騰は、発電コストを押し上げ、発電所の稼働率を低下させています。また、国内の炭鉱の人手不足による生産量の減少も、電力供給の不安定化の一因となっています。
2023年5月には、猛暑と降水量の減少により水力発電の供給が不足しました。火力発電への依存度が高まる中で、発電所の不具合が発生し、供給力が大幅に低下しました。結果として、北部地域を中心に計画停電が行われ、多くの企業の生産活動が停滞しました。
火力発電所の復旧と降水量の増加により電力不足は一時的に緩和されましたが、石炭火力発電への依存、再生可能エネルギーへの転換の遅れなど、電力供給の基盤となる構造的な問題が依然として残っています。電力不足の長期化はベトナムの経済成長や輸出産業に深刻な影響を及ぼす恐れがあり、企業の生産拠点移転や観光業への影響など、経済活動全体への打撃も懸念されています。
この問題を解決するためベトナム政府は、安定した電力供給の確保と2050年までの温室効果ガス(GHG)排出量実質ゼロを目指し、脱酸素・再生可能エネルギーの推進に取り組んでいます。しかし、投資拡大計画の不透明さや、関連する政策・法制度の整備の遅れにより、多くのプロジェクトが停滞しています。
人件費の上昇と高齢化
三つ目の課題は、人件費の上昇です。2021年の最低賃金は新型コロナウイルスの影響により据え置きになったものの、ベトナムでは人件費の上昇が急速に進んでいます。
2024年7月には、地域別に設定している最低賃金が引き上げられました、2022年7月1日に平均6.0%引き上げて以来2年ぶりの改定です。前回の改定から時間単位の最低賃金も加わり、2020年1月~2024年7月の4年半で3回行われています。今後もGDPの伸び率に合わせ増加する可能性が高いと言われており、ベトナムへ安価な労働力を期待して進出する企業のリスクとなっています。
また賃金上昇とともに懸念されるのが、労働人口の構成比の変化です。ベトナムは人口構成が若く労働人口が豊富な国というイメージがありますが、 2011年にはすでに高齢化社会入りを果たしており、2036年には高齢者人口比率が14%を超える高齢社会へと移行すると予測されています。2050年には25%を超える超高齢社会になる可能性も指摘されており、労働力不足が深刻化する懸念があります。
合計特殊出生率の低下と平均寿命の伸びが主な要因で、世界的に見ても速いペースで高齢化が進んでいます。中長期的に見ると、毎年のように上がる平均賃金の負担、労働力不足の問題によって外資企業離れが進むとみられ、労働生産性を高めることが課題となっていくでしょう。
今後の見通し
 2022年以降の経済成長と課題
2022年以降の経済成長と課題
ベトナム経済は、コロナ禍からの回復が期待される中、2022年には高い成長を遂げました。しかし2022年以降は、世界的な経済の減速や、国内の不動産市場の調整など、新たな課題も浮上しています。
・2022年の高成長とその後
2022年は、外国人観光客の増加や国内消費の回復により、25年ぶりの高成長となる前年比8.0%を達成しました。しかし、同年後半には、世界的なスマートフォン需要の減少や中国経済の減速に伴い輸出が落ち込み、GDPの25%を占める製造業の成長が鈍化しました。また、不動産デベロッパーの違法な社債取引に対する政府の規制強化により、多くの不動産・建設プロジェクトが中断し、不動産市場も停滞しました。
・2023年の成長鈍化と回復
2023年は、世界的なインフレや金融引き締め、地政学的なリスクの高まりといった外部環境の悪化に加え、国内では不動産市場の調整が長期化し、成長率は目標を下回る5.1%にとどまりました。しかし、第4四半期には、政府の経済促進政策や観光業の回復により、成長率が改善しました。
産業別では、世界的な需要低迷の影響を受けた製造業と建設業により、工業全体の成長率は3.02%と鈍化し、特に製造業は過去13年で最低となる3.62%の成長率でした。一方、経済の主力であるサービス業の成長率は小売業と観光業が好調で、2023年は6.82%を超え、2020年と2021年の水準を上回りました。
・2024年の見通し
2024年は、政府がインフラ整備や投資環境の改善、企業の国際競争力を高めるためのデジタル化推進など、さまざまな政策を展開しており、経済成長率は6.5~7.0%に達すると予想されています。
2024年第3四半期には、大型台風の影響にもかかわらず、前年同期比7.4%の成長を達成し、第2四半期の7.1%を上回る堅調な結果となりました。製造業部門は11.41%の力強い成長で経済をけん引し、サービス業も好調を維持しています。運輸・倉庫部門は10%超の成長を記録し、1~9月期の小売り・サービス売上高は8.8%増、訪越外国人数は43.0%増の1,270万人に達しました。
しかし、世界経済の不透明感や、国内の不動産市場の回復の遅れなどが依然としてリスクとして残っています。政府は、これらの課題に対処しつつ、持続可能な成長を実現するための政策をさらに強化していく必要があるでしょう。
「チャイナプラスワン」として存在感を増す
「チャイナプラスワン」とは、中国に集中していた生産拠点や調達先を他国にも分散させる戦略です。従来、多くのグローバル企業は製造コストの優位性から中国に生産拠点を集中させてきました。しかし、新型コロナウイルスによる都市封鎖とそれに伴う国際物流の混乱により、中国一極集中型のサプライチェーン構造が持つ脆弱性が露呈しました。その結果、企業はリスク分散を迫られ、中国以外への生産拠点設立を加速させています。
中国への集中がもたらすリスクは、米中貿易摩擦などの地政学リスク、人件費上昇などの経済リスク、そして人権問題に関する国際的な懸念など多岐にわたります。このような状況下で、ベトナムは中国と似た事業環境、すなわち低コスト労働力、政府の支援、サプライチェーンの整備といった条件を備えていることから、代替生産拠点として注目を集めています。
中国企業の進出も急増しています。中国国内の人件費高騰や米国による追加関税の影響を軽減するため、海外への生産移管を進めているのです。企業のリスク分散ニーズにより、地理的に中国に隣接するベトナムの存在感は高まっており、今後も代替拠点としての優位性を保つため、電力供給やインフラの整備が急務となっています。
出典:ジェトロ「第3四半期のGDP成長率は前年同期比7.4%、伸び率が加速」
まとめ
ベトナムは、ドイモイ政策による市場経済への転換を契機として、目覚ましい経済成長を遂げてきました。しかし、インフラ整備の不足、電力不足、人件費の上昇といった課題を抱えています。政府はこれらの課題に対し、外資誘致による投資環境の改善や、中小企業支援を通じた経済の多様化といった政策を推進しています。これにより、将来的にはインフラ整備が加速し、電力供給が安定化するとともに、人材育成によって人件費問題も緩和されることが期待されています。
日本企業にとってベトナムは魅力的な進出候補地の一つです。ただし、進出にあたっては、さまざまなリスクを慎重に検討する必要があります。成功を収めるためには、現地事情を十分に把握し、長期的な視点でビジネスを展開することが重要です。
東京都が主催する「X-HUB TOKYO」事業では、都内スタートアップ企業の海外進出を支援するさまざまなプログラムを実施しています。海外マーケット攻略に必要な情報提供や海外進出に必要なノウハウを学ぶセミナーなど、幅広いサポートを提供していますので、ぜひ最新のイベント情報をチェックしてみてください。