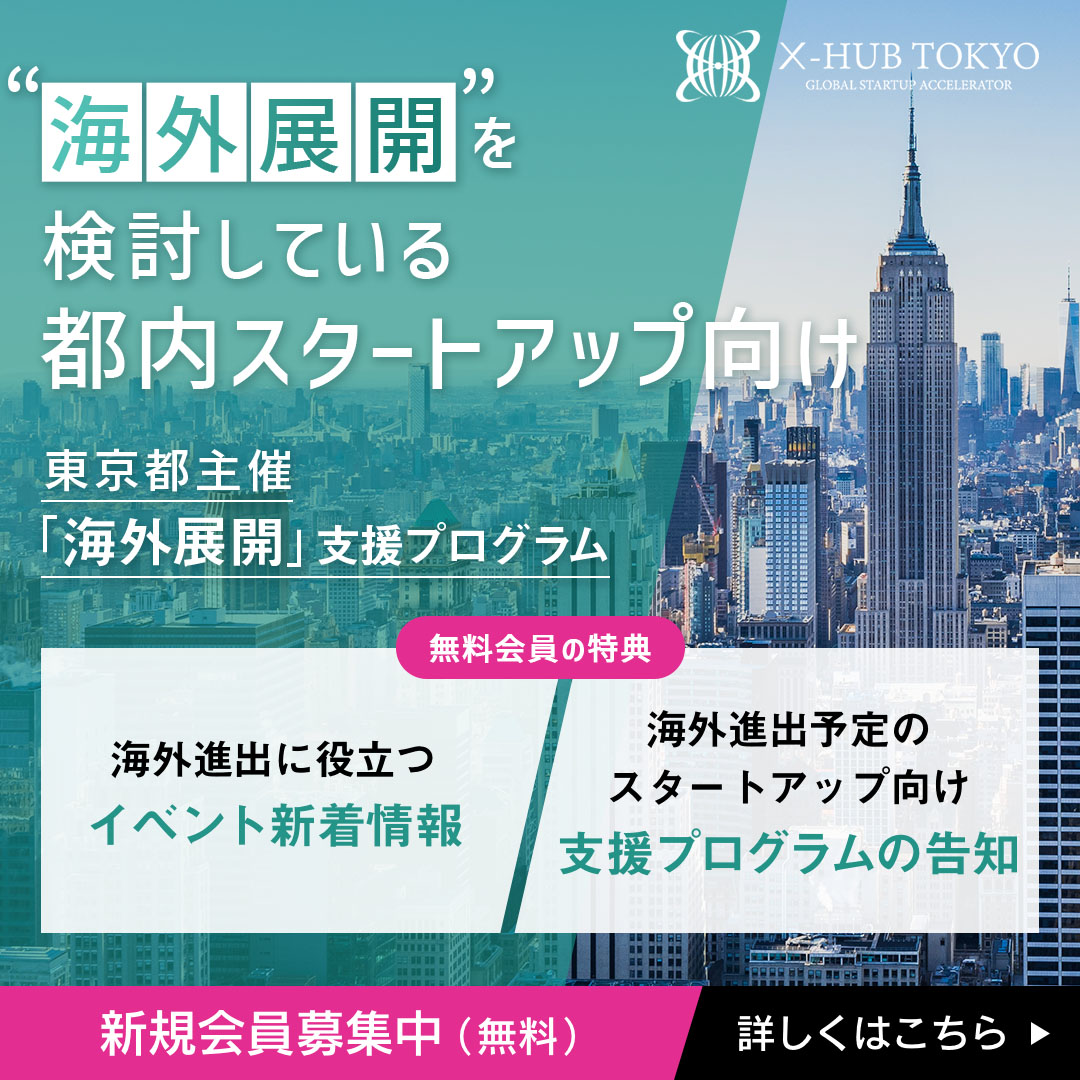海外ビジネスへの参入には、海外市場調査、展示会への出展、現地パートナーの開拓など、準備段階から多様な費用が発生します。特に中小企業では、こうした初期投資が負担となり、計画どおりに進出を進められないケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、国や自治体では返済不要で活用できる補助金・助成金制度を整備しています。あわせて、成長段階にあるスタートアップを対象とした伴走支援型プログラムも広がっており、企業規模や事業フェーズに応じた支援を得られる環境が整いつつあります。
本記事では、海外進出を検討する企業が利用できる主要な補助金・助成金・支援制度を目的別に紹介します。各制度の特徴を理解し、自社の計画に適した支援を組み合わせることで、海外展開の実現可能性を高めていきましょう。
目次
海外展開に活用できる補助金・助成金の全体像
海外展開に活用できる補助金・助成金は、制度ごとに目的や対象経費が異なり、事業の進め方や検討段階に応じて適した支援も変わります。市場調査、展示会出展、知的財産権の取得、ブランド構築、実証事業など、海外展開に必要となる取り組みは多岐にわたるため、まずは制度の全体像を把握しておくことが重要です。
海外展開向けの公的支援制度は、主に次の3つの目的に分類できます。
1. 海外での知的財産権取得(外国出願・商標保護等)
模倣防止やブランド保護の観点から、海外展開の初期段階で重要となる取り組みです。
2. 海外販路開拓・ブランド構築(展示会・EC・多言語化・PR等)
展示会・商談会の出展や越境ECの活用、多言語化、PR施策など、海外市場で顧客接点を築くための活動に加え、市場適合を高めるための製品・サービス開発、デザイン改善、ブランド価値向上に向けた取り組みを支援します。
3. 実証・社会課題解決(海外実証、技術協力等)
現地でのニーズ検証や実証実験、社会課題の解決に向けた技術協力など、実装に向けた活動を支援します。
ここからは、海外展開に関する補助金・支援制度を、知的財産権の取得、海外向けの販路開拓・ブランド構築、海外での実証事業といった目的別に整理して紹介します。あわせて、スタートアップ向け支援制度や、融資・保証・出資など補助金以外の資金調達手段についても取り上げます。
海外での知的財産権取得に使える補助金

海外展開の初期段階では、特許・商標・意匠などの知的財産権を適切に取得しておくことが重要です。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストが発生し、中小企業にとって大きな負担となりがちです。そのため、特許庁が実施する「中小企業等外国出願支援事業(外国出願補助金)」などの公的制度を活用することが有効です。
外国出願補助金(中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金)
特許庁で実施している補助金制度です。受付は日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等を通じて行います。中小企業の外国出願促進のための補助金で、海外進出を計画している中小企業の出願費用の一部を助成するものです。補助対象になる費用は、出願料や国内・現地代理人費用、翻訳費用などです。
日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等では公募期間が異なるため、それぞれ確認するようにしてください。
| 補助金額 | 1企業あたりの上限額300万円(複数案件の場合) |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象費用の2分の1以内 |
| 案件ごとの上限 | 特許150万円、実用新案・意匠・商標出願60万円、冒認対策商標30万円 |
| 公募 | 令和5年度は年に3回実施 |
| 対象 | 中小企業者または中小企業者で構成されるグループ (構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者) ただし、みなし大企業を除く |
| 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等 |
出典:特許庁「外国出願に要する費用の半額を補助します」
海外販路開拓・ブランド構築に活用できる補助金
海外市場で継続的に事業を展開していくためには、単発的な販路開拓にとどまらず、製品・サービスの改良やデザイン改善、ブランドの確立を含めた中長期的な取り組みが求められます。ここでは、販路開拓とブランド構築を一体的に支援する補助金制度として、規模や対象範囲の広い補助金制度や、地方自治体が実施する補助金を紹介します。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(グローバル枠)
中小企業庁および独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する補助金で、国内の生産性向上や新製品・サービス開発等に必要な設備・システム投資を支援します。グローバル枠に申請する場合は、基本要件に加えて、以下のいずれかに該当する海外関連事業を実施する企業が対象となります。
- 海外への直接投資
- 海外市場開拓(輸出)
- インバウンド対応
- 海外企業との共同事業
特に 海外市場開拓(輸出) を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 製品等の最終販売先の 1/2 以上が海外顧客となる事業計画であること
- 計画期間中の売上累計額が補助額を上回る計画であること
また輸出事業では、従来の補助対象経費(機械装置・システム構築費など)に加え、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費なども対象となるため、設備投資と輸出販促を一体的に支援できます。
| 補助金額 | 100万~3,000万円 ※大幅な賃上げに取り組まれる場合は更に上がります |
|---|---|
| 補助率 | 中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者は2/3 |
| 公募 | 年に複数回 |
| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知財関連経費、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝費など |
地方自治体の海外販路開拓補助金
東京都、大阪府、愛知県など、多くの地方自治体では、地域経済を担う中小企業や小規模事業者の海外展開を後押しするため、独自の販路開拓補助金を実施しています。制度内容は自治体によって異なりますが、海外展示会や商談会への参加費用、海外向けPR・広告制作、パンフレットやウェブサイトの多言語化、海外バイヤーの招へいなど、販路開拓に必要となる幅広い活動が対象となります。
自治体が実施する補助金は、補助上限額が数十万円〜100万円程度に設定されることが多く、比較的小規模なプロモーション活動や調査に取り組む段階でも利用しやすい点が特徴です。こうした制度は海外進出の初期段階を支える実用的な支援であり、自治体の商工会・産業振興センターなどの相談窓口と組み合わせることで、より効果的な販路開拓が期待できます。
参考:
東京都「市場開拓助成事業」
愛知県「海外販路開拓支援事業補助金」
宮城県「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」
大阪府堺市「堺市グローバル展開促進事業補助金」
越境EC・展示会出展による海外販路開拓支援
海外市場への進出初期や新たな地域への展開では、展示会出展や商談会への参加、越境ECを活用したオンライン販売など、初期段階から取り組みやすい手法による販路開拓が用いられてます。設備投資や製品開発を前提としない形で活用できる、展示会出展支援や越境EC関連の公的支援制度を紹介します。
越境EC・デジタル販路開拓支援(ジェトロによる実務サポート)
越境ECは、初期投資を抑えながら海外の消費者へ直接アクセスできる手段として注目が高まっています。特に日本貿易振興機構(ジェトロ)は、越境ECの立ち上げから販売促進までを一貫して支援するサービスを提供しており、デジタルを活用した海外販路の構築を後押ししています。
提供される主な支援は次のとおりです。
- JAPAN STORE プログラム(米国・英国 Amazonでの販売支援)
- E-commerce Academy(越境ECに関する基礎・実務講座)
- JAPAN MALL 事業(海外EC事業者との連携販売支援)
- 貿易投資相談(輸出・EC・物流に関する実務相談)
- 海外ミニ調査サービス(市場性・ニーズの簡易調査)
- JETRO e-Venue(オンライン商談・バイヤーマッチング)
これらは、商品ページの改善、多言語対応、物流・税関対応、海外ユーザー向けのPR、バイヤー商談など、越境EC運用に必要なプロセスを幅広くカバーしています。オンラインで段階的に海外市場へアクセスしたい企業にとって、リスクを抑えて市場性を検証できる実務的な支援といえます。
出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「越境EC」
海外展示会・商談会出展支援(ジェトロによる出展サポート)
海外市場での認知度向上や取引先獲得には、展示会・商談会への出展が依然として重要な手法です。日本貿易振興機構(ジェトロ)では、海外見本市の ジャパンブース(ジャパンパビリオン) への出展を支援しており、手続きや準備負担を軽減する仕組みが整えられています。
提供される主な支援は次のとおりです。
- 出品申込み、ブース設営、ブースのデザインなどをパッケージ化
- 出品物の通関・輸送のサポート
- 対象展示会によっては、出展経費の一部について補助が適用される場合あり
単独出展に比べ、費用・労力を抑えつつ海外バイヤーとの商談機会を拡大できる点がメリットです。
出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「展示会・商談会への出展支援」
海外での実証・社会課題解決に向けた支援プログラム・補助金
海外市場へ事業を展開する際には、現地でのニーズ検証や実証実験を行うことが極めて重要です。しかし、海外実証は費用・リスクの両面で負担が大きくなるため、公的な支援制度や補助金を活用することが有効です。
普及・実証・ビジネス化事業(JICA)
国際協力機構(JICA)が実施する支援プログラムで、途上国の課題解決に貢献できるビジネスの事業化を目指す中小企業等を対象としています。企業から事業提案書を公募し、採択された企業に対して、ビジネスモデルの検証や将来的なODA事業への活用可能性の検討を支援します。
この事業では、現地調査、専門家派遣、サンプル機材の輸送、実証フィールドの確保など、海外での実証に必要となる多様な活動が支援対象となります。一方で、事業の対象国がJICA事務所または支所が設置されているODA対象国に限られる点には注意が必要です。また、提案する製品・サービス・技術等については、日本国内または海外で一定の販売実績があることが前提とされています。
| 項目 | 中小企業支援型 | SDGsビジネス支援型 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 上限1億円(大規模案件は1.5億円、特定案件は2億円) | 上限5,000万円 |
| 公募 | 年1回 | 年1回 |
| 対象 | 中小企業、中堅企業、中小企業団体 | 中小企業/中堅企業以外の営利法人・非営利法人、または中小企業支援型を2回実施済みの法人 |
出典:
独立行政法人 国際協力機構「普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)
独立行政法人 国際協力機構「普及・実証・ビジネス化事業(SDGsビジネス支援型)」
技術協力活用型・新興国市場開拓事業費補助金(社会課題解決型国際共同開発事業(製品・サービス開発等支援事業))
名称:「J-Partnership 製品・サービス開発等支援事業補助金」
経済産業省が公募している事業で、アフリカ諸国やインド、中南米をはじめとする新興国・開発途上国の社会問題解決のための製品・サービスの事業展開を目指す企業が対象です。
「J-Partnership 製品・サービス開発等支援事業補助金」という名称で、製品・サービスの開発や実証・評価など、本事業終了後2年以内に事業化を目指すビジネスプランに対し、事業開発にかかる費用の一部を補助金として提供します。
| 補助金額 | 一社最大1,000万円 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費のうち、中堅/中小企業は2/3、大企業は1/3 |
出典:J-Partnership事務局「J-Partnership」
スタートアップ向け海外展開支援制度

スタートアップ企業の海外展開では、補助金や融資といった資金支援に加え、事業モデルの検証、海外ネットワークの構築、専門家による助言など、非資金面での支援が重要となるケースも少なくありません。
こうした資金提供を伴わない、あるいは間接的に成長を支援する制度として、国や自治体、独立行政法人が実施するスタートアップ向け海外展開支援プログラムを紹介します。
インキュベーションプログラム(創業支援型)
創業初期のスタートアップを対象とした中長期型の支援制度であり、日本貿易振興機構(ジェトロ)や中小企業基盤整備機構(中小機構)などが中心となって実施しています。
このプログラムでは、事業アイデアの整理や検証、事業計画の策定支援、資金調達に関する助言が行われるほか、ワークスペースの提供やメンターによる継続的な指導などを通じて、事業立ち上げを総合的にサポートします。また、スタートアップ、投資家、専門家とのネットワーク形成を促進し、協働の機会を創出します。
アクセラレータープログラム(成長加速型)
短期間で事業成長を加速させることを目的とした集中型プログラムです。東京都が運営する「X-HUB TOKYO」をはじめ、経済産業省や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)、地方自治体などが国際的なプログラムを実施しています。
数ヶ月〜半年程度の期間で実施されることが多く、事業計画の精査、資金調達に関する専門家の助言、ピッチトレーニング、メンタリング、投資家との面談やピッチイベントが提供され、海外展開に向けた実践的な支援が受けられます。
メンタープログラム(個別指導型)
地方自治体の産業振興センターや商工会議所などが実施する制度で、経験豊富な起業家や業界の専門家がメンターとして参画し、個別の課題に対する助言を行います。ビジネス戦略やマーケティング戦略の見直し、組織運営に関する課題への対応、定期的なフィードバックを通じた事業方針の明確化など、企業が直面する実務的な課題に応じて柔軟に支援が提供されます。
プログラム活用における注意点
スタートアップ向けの支援プログラムは、それぞれ対象となる企業規模や事業ステージ、提供されるサポート内容や期間が大きく異なるため、自社の事業ステージやニーズを把握し、最適なプログラムを選ぶことが重要です。また、公募期間が短く設定されることが多いため、募集要項を十分に確認し、余裕を持って申請準備を行いましょう。
提出する事業計画書は審査において中心的な役割を果たすため、海外展開の背景、取り組む事業の具体性、実現可能性を明確に示し、説得力のある構成に仕上げることが求められます。面接審査がある場合には、事業の意義や将来性に関する質問に的確に回答できるよう、具体的な質問への対策もしておきましょう。
補助金以外の資金調達(融資・保証・出資)
海外展開では、補助金・助成金によって初期費用の一部を補える一方、支援プログラムは事業検証やネットワーク構築など、主に非資金面での支援を担います。
実際には、これらを活用しても現地法人設立や事業拡大に伴う資金需要が生じるケースも多く、融資・保証・出資といった資金調達手段を併せて検討することが重要となります。
中堅・中小企業向け融資
国際協力銀行(JBIC)が行っている融資で、開発途上国へ進出する中堅・中小企業に対して日本の金融機関と協調融資の下で長期融資します。企業規模は、中小企業であれば資本金3億円以下または常時使用する従業員数300名以下(製造業の場合)、中堅企業であれば資本金10億円未満が対象。
資金用途は、対象国の事業において必要な設備投資資金(新規、増設、更新)やM&A資金等の長期資金です。原則所要資金の一定割合(7割)を融資割合の上限として、民間金融機関(地銀/信金/メガバンク等)と協調して融資を行い、融資金額についての定めはありません。
出典:国際協力銀行「中堅・中小企業分野」
海外展開・事業再編資金
日本政策金融公庫による融資で、海外展開や海外事業の再編を必要としている企業へ長期運転資金や設備資金を融資します。直接貸付の場合には14億4千万円、代理貸付の場合には1億2千万円が融資限度額です。
基準利率は上限2.5%、信用リスクや融資期間に応じて所定の利率が適用されます。返済期間は、設備資金であれば20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金であれば7年以内(うち据置期間2年以内)が基本です。
出典:日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金」
スタンドバイ・クレジット制度
日本政策金融公庫や地方銀行、商工組合中央金庫(商工中金)等が行っている、現地法人の資金調達のための制度です。海外現地法人が現地金融機関から現地流通通貨建ての融資を受ける際に、現地金融機関に対し信用状を発行します。日本政策金融公庫や銀行等が信用保証をすることで、融資が受けやすくなるようサポートします。
日本政策金融公庫の場合、保証限度額は1法人あたり4億5千万円。信用リスクや信用状の有効期間等に応じて所定の補償料率が適用されます。
出典:日本政策金融公庫「スタンドバイ・クレジット制度」
特定信用状関連保証(全国信用保証協会)
全国信用保証協会の行う、資金調達をサポートする制度です。海外子会社を有する国内中小企業が対象で、海外子会社が現地の金融機関から融資を受ける際、国内の金融機関が発行する「信用状」に関しての債務保証を提供します。国内の金融機関に対して、国内の親会社が負担する債務を信用保証協会が保証することで、信用力を高めます。
資金使途は海外子会社の現地金融機関からの借入金であり、信用状の額面は2億5千万円、限度額は2億円です。運転資金や設備資金のどちらにも活用することができ、「一般保証」とは別枠で利用することも可能です。
出典:一般社団法人 全国信用保証協会連合会「海外展開をお考えの方」
ファンド出資(中小企業基盤整備機構:中小機構)
中小企業基盤整備機構(中小機構)が行っているファンド出資制度で、中小企業に対する投資事業を行う民間機関等と共同で投資ファンドを組成し、ベンチャーや中小企業への資金提供を行います。新事業展開の促進や事業の拡大、事業再生などを支援する仕組みです。
ファンド出資は、創業または成長期の中小企業を支援する「起業支援ファンド」、成長が見込まれる新事業展開を支援する「中小企業成長支援ファンド」、再生に取り組む中小企業を支援する「中小企業再生ファンド」の3種類に分かれています。
出典:中小機構「ファンド出資」
補助金・助成金を活用する際の注意点

補助金や助成金は海外展開の初期負担を軽減する有効な手段の一つですが、申請すれば必ず受給できるわけではなく、制度ごとに要件や条件が細かく定められています。多くの制度は全額補助ではなく補助率に応じた自己負担が生じ、資金の受取も事業完了後の精算払い(立替が必要)となる場合が一般的です。
これらの制度は毎年見直しや改訂が行われるため、最新情報を踏まえた準備が欠かせません。ここでは、申請時だけでなく採択後まで見据えた、特に注意すべき実務上のポイントを整理します。
1. 補助金と助成金の違いを理解する
補助金は審査を経て採択される制度であり、事業の新規性や政策目的との適合性が重視されます。一方、助成金は要件を満たすことで受給できる制度が中心ですが、海外展開に直接活用できるものは限られます。両制度の性質を理解したうえで、自社に最適な支援策を選択していくことが重要です。
2. 申請要件と募集時期の確認
補助金は企業規模・事業内容・地域要件などが制度ごとに異なり、補助率や対象経費、上限額も年度ごとに変わります。公募期間は短いケースが多いため、最新の公募要領を確認し、自社の事業スケジュールと整合するかを事前に検討しておく必要があります。
3. 審査で重視される事業計画書の質
審査では、海外市場のニーズ、自社の強みや競争優位性、数値計画の妥当性、補助金活用による効果、リスク対策などを客観的に示すことが求められます。事業の必要性と実現可能性を具体的に説明できるかが採択の重要なポイントとなります。
4. 対象経費・証憑管理への理解
補助金は対象経費が厳格に定められており、通常の営業経費や本社の管理費、飲食費・交際費などは対象外です。また、領収書・契約書・見積書などの証憑管理を適切に行うことが必要で、書類不備は減額や不採択につながる場合があります。
5. 実施時期の制約と採択後の管理
補助対象となるのは「補助対象期間内の支出」に限られます。申請前に契約・支出した費用は原則対象外であるため、展示会や実証など時期が決まっている事業では特に注意が必要です。また、採択後は進捗報告・実績報告などの事務作業が求められます。
6. 複数制度の併用可否の確認
制度によっては、他の補助金との併用が禁止されている場合や、同一経費への重複補助が認められない場合があります。また、採択後に新たな補助金へ申請する際にも制約が発生するケースがあります。公募要領やFAQで必ず併用可否を事前に確認し、必要に応じて支援機関へ相談することが重要です。
まとめ
海外展開を進めるにあたっては、知的財産権の取得、販路開拓、実証事業、ブランド構築、さらには現地法人の設備投資や運転資金の確保など、多岐にわたる準備が必要になります。こうした費用負担を自社のみで賄うことが難しい場合には、目的に応じた補助金・助成金や各種支援制度を活用することで、資金面のハードルを抑えられる場合があります。
一方で、補助金・助成金の活用には、申請要件の確認、事業計画書のブラッシュアップ、対象経費の整理、証憑(領収書・契約書・見積書等)の管理、公募スケジュールへの対応など、一定の準備や事務作業が必要となります。制度の特性や留意点を把握したうえで、必要に応じて支援機関や専門家の助言を得ながら、自社の計画と整合した制度活用を進めていきましょう。
なお、制度の内容・条件・公募時期は年度や社会情勢により変更される可能性があります。各制度やプログラムの公式ウェブサイト・窓口等で最新情報をこまめに確認し、海外展開に向けた事業計画を継続的に更新することで、より効果的な支援獲得につなげられるでしょう。