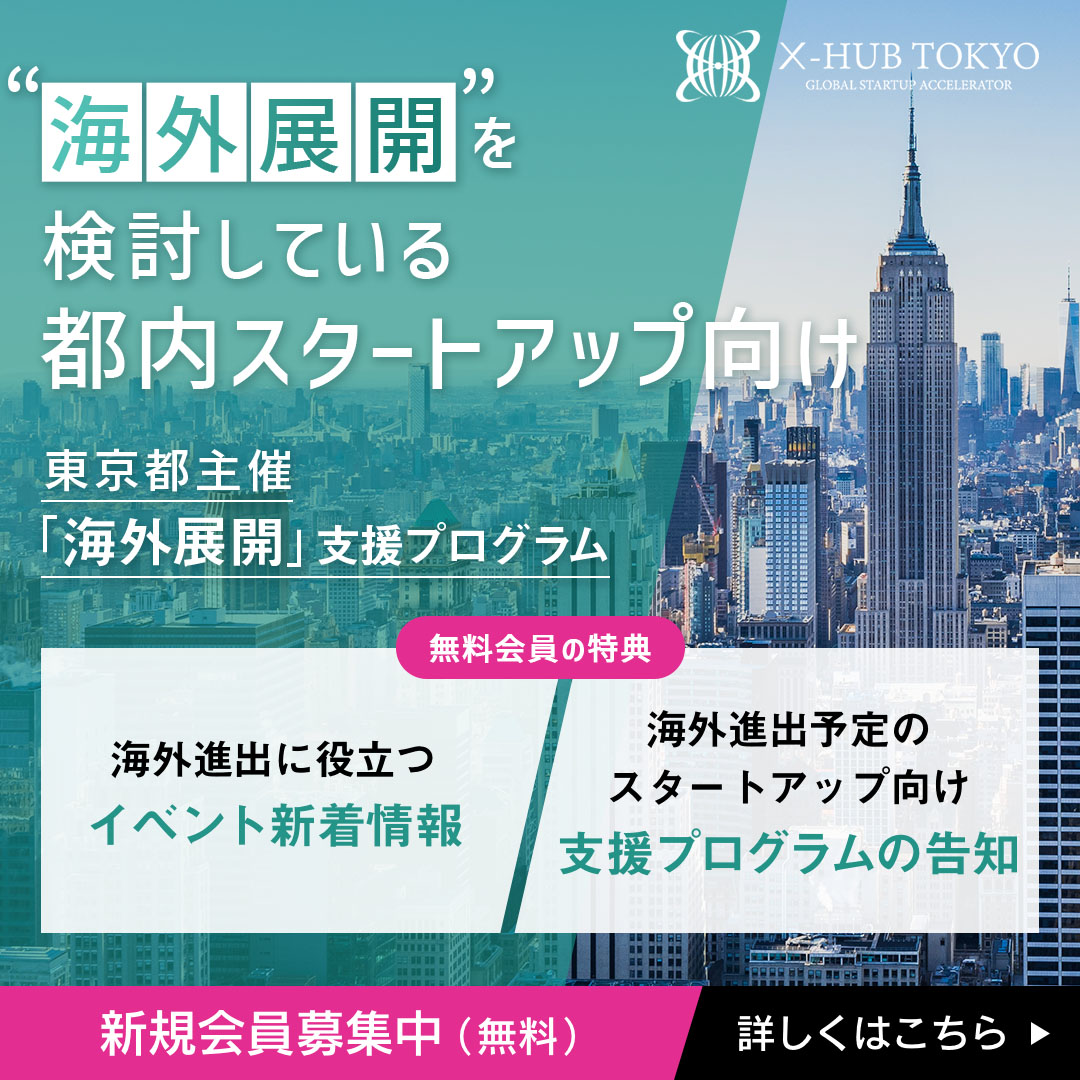グローバル化が進む現代において、海外市場への展開は企業の持続的な成長に不可欠です。海外ビジネスの成功には、現地の法規制、特に税制の理解が重要な要素の一つとなります。
日本の消費税とは異なる海外のVAT(付加価値税)制度を正しく理解することで、海外展開時のトラブルを避け、予期せぬ追徴課税や取引先との契約トラブル、法的リスクを回避できます。この記事では、海外展開する企業が押さえておきたいVATの基本的な仕組みと主要国・地域の制度、そして注意点を解説します。
まずは、VATの定義や特徴的な仕組み、日本の消費税との違いなど、基本的な知識を押さえましょう。
VATとは?
付加価値税(Value-Added Tax=VAT)とは、商品やサービスの取引ごとに発生する「付加価値」に対して課される間接税です。これは160か国以上で導入(2021年時点)されている国際標準の税制で、日本の消費税と同様に最終消費者が税負担を担うものです。
しかし、VATは日本の消費税とよく似ている一方で、事業者ごとの登録義務、申告・納付のフロー、税額計算方法などに多くの違いがあるため、海外ビジネスを展開する際は細部まで十分に理解する必要があります。
仕入税額控除の仕組み
VATの大きな特徴の一つが「仕入税額控除」です。これは事業者が、販売時に顧客から受け取ったVATから、仕入れ時に自身が支払ったVATを差し引いて納税する方式です。この仕組みによって、同じ付加価値部分への重複課税を防ぎ、最終的に消費者のみが税を負担することとなります。
たとえば、製造業者が原材料を100ドルで仕入れ(VAT10ドル支払い)、それを加工して200ドルで卸売業者に販売(VAT20ドル預かり)した場合を考えてみましょう。この製造業者が納めるVATは「預かったVAT20ドル − 支払ったVAT10ドル = 10ドル」となります。このように、VATは最終消費者に届くまでの各取引段階で公平に課税されていきます。
製品の販売にかかるVAT負担の流れ(例)
| 取引ステップ | 製造業者 | 卸売業者 |
|---|---|---|
| ①商品の 取引 |
原材料を100ドルで仕入れ、製品を200ドルで販売 | 製品を200ドルで仕入れ |
| ②VATの 動き |
・仕入時:10ドル支払(控除可能) ・販売時:20ドル受取(納税義務) |
・仕入時:20ドル支払(控除可能) |
| ③最終 納税額 |
10ドル(受取20ドル – 支払10ドル) ※仕入時に支払った10ドルは原材料生産業者が納税 |
※販売段階で決定 |
日本の消費税との違い
日本の消費税は、標準税率10%と軽減税率8%の2つの税率(いずれも地方消費税を含む)で構成されています。
一方、海外の多くの国では、食料品や書籍などに対して低い税率を適用するなど、より複雑な複数の税率体系が存在します。さらに、税率だけでなく、業種別の特別ルール、複雑な免税制度、仕入税額控除の対象範囲、申告・納付の頻度(月次、四半期、年次など)、そしてインボイス制度の運用など、日本とは多岐にわたる違いが見られます。
アメリカの売上税との違い
アメリカの「売上税(Sales Tax)」は、課税主体と課税段階において、VAT(付加価値税)とは根本的に異なります。
課税主体の点では、VATが日本の消費税のように国やEUのような共同体によって課される一方、アメリカには連邦レベルのVATは存在しません。その代わりに、各州や地方政府が独自に売上税を課しています。
課税段階においては、VATが生産から小売までの各取引段階で課税される「多段階課税」であるのに対し、アメリカの売上税は商品を小売段階で購入する際にのみ課税される「単段階課税」が適用されます。つまり、アメリカでは最終消費者が商品を購入する際に一度だけ税金が課される仕組みです。
主要国・地域の間接税制度と税率

海外の間接税制度は国や地域によって多岐にわたります。間接税とは、商品やサービスの取引を通じて課される税金で、日本の消費税や宿泊税などがその代表例です。ここでは、主要な国・地域の制度と税率を見ていきましょう。
欧州諸国:統一VAT制度とイギリスの独自制度
EU諸国では、加盟国間でルールを統一した「統一VAT制度」が運用されています。標準税率は15%以上と定められていますが、国ごとに異なります(例:ドイツ19%、フランス20%、イタリア22%)。
2021年に導入されたOSS(One-Stop Shop)制度により、EU域外の事業者がEU域内の消費者に商品(遠隔販売)やデジタルサービスを販売する場合、OSS専用の登録を行うだけで、EU域内全体の申告・納税を一括で行えるようになりました。これにより、国ごとのVAT登録が不要になり、税務管理が大幅に簡素化されています。
一方、EUを離脱したイギリスは、標準税率20%の独自のVAT制度を運用しており、EUのOSS制度の対象外です。そのため、イギリスで商品を販売する際は、英国歳入関税庁(HMRC)へのVAT登録が必須となります。
オンラインマーケットプレイス(OMP)を通じて135ポンド以下の商品を消費者に販売し、かつ直送する場合は、原則としてOMPがVATの納税を代行してくれます。しかし、135ポンドを超える商品や、B2B(事業者向け)取引、あるいは独自ドメインでの販売など、OMPが納税を代行しないケースでは、販売者自身がVAT登録・申告・納税を行う必要があります。詳細は必ずHMRCの公式サイトで確認するようにしましょう。
アジア諸国:多様なVAT・GST制度
アジア諸国でも、各国が独自のVATやGST(Goods and Services Tax、物品・サービス税)を導入しています。税率や運用ルールはさまざまで、例えばシンガポールのGSTは9%、韓国のVATは10%、タイのVATは7%です。インドでは2017年に複雑な間接税を統合してGSTが導入され、5%、12%、18%、28%という4段階の税率が設定されています。
アメリカ:州別売上税制度
アメリカの売上税は州・地方政府が管轄しており、実効税率は0%から10%超まで地域により変動します。
※各国・地域の税率は改定される可能性があるため、取引を行う際は必ず各国の税務当局の公式サイト等で最新情報を確認してください。
海外進出時の注意点

海外ビジネスにおいてVAT対応を誤ると、思わぬペナルティや取引停止のリスクが生じかねません。以下のポイントに留意し、適切な対策を講じましょう。
VAT登録が必要になるケース
VAT(付加価値税)登録とは、事業者がVATの納税義務者として各国の税務当局に登録されることを指します。登録事業者は、商品やサービスの販売時に顧客からVATを徴収し、事業活動で支払った仕入れVATを控除した上で、差額を税務当局に納付します。
EU諸国をはじめとするVAT制度導入国では、各国の定める年間売上高を超えた場合、あるいは特定の取引形態によってVAT登録が必要になります。特にEU向けの越境ECやデジタルサービス提供の場合、消費地課税の考え方に基づき、売上高にかかわらずごく少額の取引でも登録義務が発生することがあります。
VATの登録基準や手続きは国・地域ごとに大きく異なり、税制も頻繁に改定されるため、必要に応じて現地の税理士や法律専門家のサポートを検討しましょう。
越境ECビジネスの注意点
日本企業を含むEU域外の事業者がEUの消費者に商品を販売する場合、2021年7月のVAT(付加価値税)改正により、原則として売上高にかかわらず販売先の国でVATが課税されることになりました。これに伴い、OSS(One Stop Shop)制度が導入され、EU域内各国への登録・申告手続きは簡素化されています。
しかし、OSS制度の利用にはEU域内の売上基準や対象商品・サービスの制限といった一定の条件があり、正確な申告・納税、詳細な記録保持、システム対応、そして適切な価格設定など、適切な運用が求められます。
一方、アメリカ市場向けの越境ECでは、各州が定めるEconomic Nexus(経済的関連性)ルールに注意が必要です。このルールにより、企業が特定の州における売上基準を満たすと、その州の売上税(Sales Tax)徴収義務が発生するため、アメリカへの展開を検討する際は各州の基準を個別に確認し、対応する必要があります。
デジタルサービスの課税ルール
EU諸国および多くの国では、アプリやソフトウェア、動画配信などのデジタルサービスを提供する際、課税ルールは顧客が消費者か事業者か(B2CかB2Bか)で異なります。
具体的には、B2C(消費者向け)では消費者の居住地が、B2B(事業者向け)では購入者の事業所所在地が課税地となります。顧客の実際の所在地を特定するためには、通常、IPアドレスや課金先情報などが利用されますが、顧客がVPNを利用する場合、所在地特定が難航することがあります。
このため、デジタルサービスを提供する事業者は、エンドユーザーがVPNを利用しているケースを考慮し、利用先の国・地域における正確な課金先情報を保持するなど、顧客の実際の所在地特定に向けた情報管理体制の構築が求められます。
まとめ
VATは、海外展開を目指す企業にとって必ず理解すべき税制です。世界の多くの国で採用されており、仕入税額控除を通じて最終消費者が税を負担する仕組みですが、その運用は国によって大きく異なります。
税率、登録基準、そして越境ECやデジタルサービスに適用される複雑なルールを事前に把握し、適切な対応策を講じることが重要です。継続的な情報収集と対応が、海外ビジネスの安定した成長に繋がります。
東京都が主催するX-HUB TOKYOは、都内スタートアップの海外進出を強力に後押しします。海外展開に必要なノウハウの習得から、海外のVCや大企業とのネットワーク構築まで、多角的なサポートを提供しています。より詳しい情報や、各プログラムへの参加にご興味があれば、ぜひX-HUB TOKYOの最新イベント情報をチェックして、グローバルビジネスを加速させましょう。