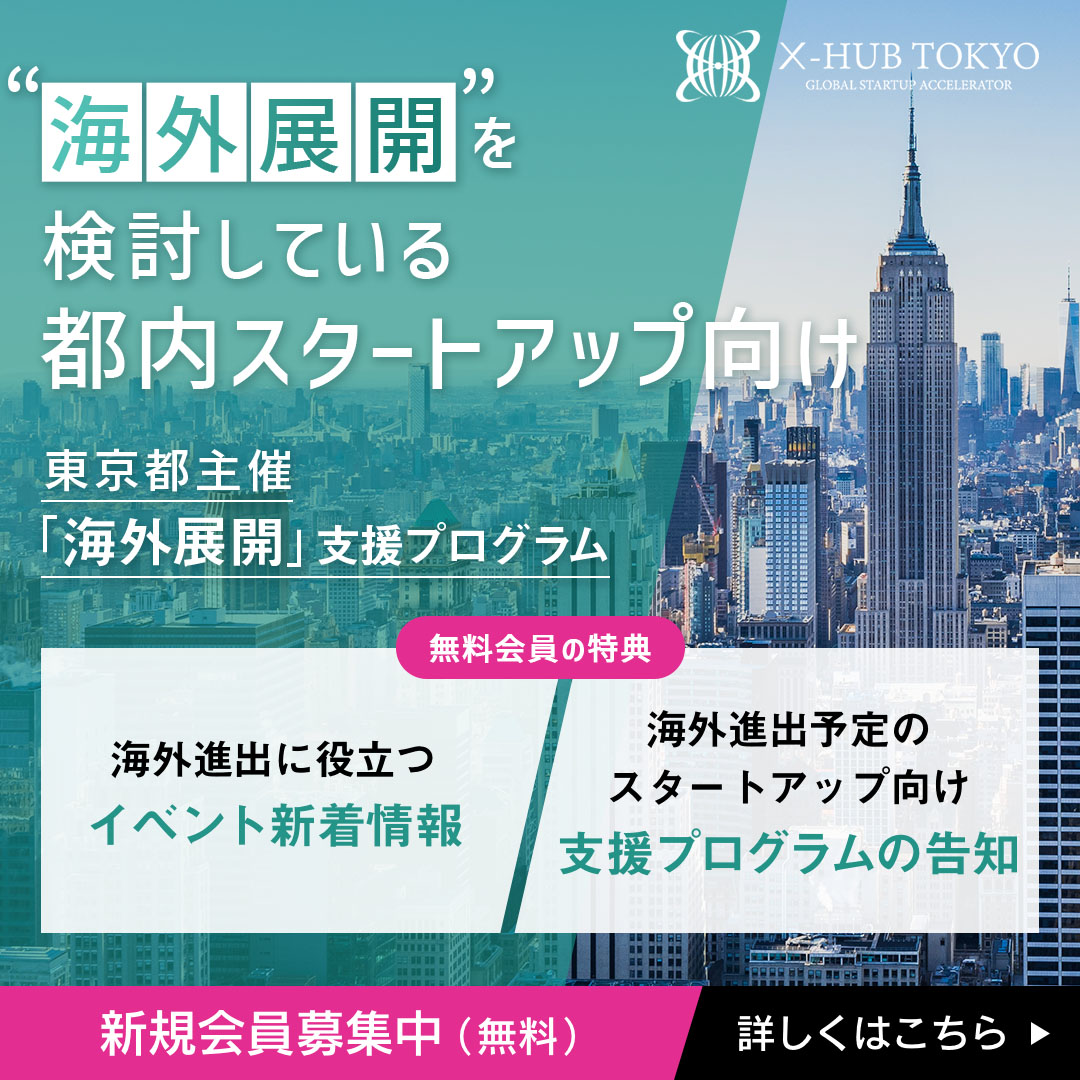海外進出のためには、ノウハウや情報なども必要ですが、現実的な資金面の確保も大切です。資金に余裕がない場合には、融資や補助金・助成金などの制度を検討しましょう。
海外進出へ向けた資金調達の必要性
海外進出を考えるにあたって、まず必要となるのは資金です。中小企業やベンチャー企業などではとくに、自己資金だけでその予算をカバーすることは難しく、資金調達のために利用できる融資や補助金・助成金制度などを利用することになります。
融資や補助金・助成金制度は、公的な機関を中心に行われており、海外進出のための貸付はより有利な条件下での利用が可能です。利用するには諸条件を満たす必要がありますが、活用できれば非常に便利な制度となっています。
このようなサポート制度には、資金面のサポートだけでなく、情報の提供や事業計画策定・販路開拓、信用状発行などの支援も含まれています。海外進出における最初の足掛かりとして、こうした支援も検討してみるとよいでしょう。
補助金と助成金の違い
海外進出の際に融資とともに検討されるものに、海外進出に向けて利用できる補助金や助成金があります。融資と補助金・助成金の大きな違いは、返済の有無です。
融資は企業が事業用資金のために金融機関からお金を借りる資金調達の手段で、元金に利息を加えて返済する必要があり、返済期間や返済方法などはさまざまです。比べて、補助金や助成金は原則として返済義務はありません。ただし、事業計画が達成できなかった場合や不正受給が発覚した場合には、返還を求められることがあります。
補助金と助成金は、事業活動の支援を目的とした公的資金という点で共通していますが、いくつかの違いがあります。どちらも事業者にとって魅力的な資金調達方法ですが、それぞれの特徴を理解した上で、自社の事業に最適なものを選択しましょう。
給付対象の違い
補助金は、経済産業分野における特定の事業やプロジェクトを対象に給付されます。設備投資や新技術の研究開発など、国や地方公共団体の政策目標に合致した事業が対象となります。それに対し助成金は、人材育成や雇用創出、労働環境の改善などを目的として給付されます。
交付管轄の違い
補助金は経済産業省およびその外局である中小企業庁、関連独立行政法人などが管理し、各省庁や自治体、民間団体などによるさまざまな補助金があります。助成金は厚生労働省が管轄し、厚生労働省管轄の都道府県労働局が管理しています。
交付要件の違い
補助金の交付を受けるためには、事業計画書などの提出が求められ、審査に通過する必要があります。助成金の交付要件は助成金の種類によって異なりますが、補助金と比べ、審査基準が緩やかな傾向にあります。
日本政策金融公庫による融資

続いて、具体的な制度の内容について見ていきましょう。
「海外展開・事業再編資金」は、日本政策金融公庫による融資です。財務省の財政投融資により、小規模事業者や中小企業の海外進出・事業再編を支援します。「海外展開・事業再編資金」は、国民生活事業と中小企業事業に分かれており、それぞれサポートする対象が異なります。
海外展開・事業再編資金「国民生活事業」
国民生活事業は海外展開を開始・拡大する中小企業が対象の融資です。本社が日本国内にあることを前提とし、海外展開事業が事業の延長と認められる程度の規模を有するものであることが条件です。また、取引先の海外進出に伴う海外展開、原材料の供給事情や労働力不足、国内市場の問題から海外進出をする企業など、いくつかの項目に該当する企業を支援しています。
具体的には海外進出や事業再編のための資金として、設備や運転資金を外貨で貸し付けます。
| 資金の使い道 | 当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金 ※海外企業に対する転貸資金は要問合せ |
|---|---|
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金は4,800万円) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) |
| ※海外企業への転貸資金 進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合、 その他やむを得ない事情がある場合に限り、以下の返済期間を適用 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内) |
海外展開・事業再編資金「中小企業事業」
「中小企業事業」は、これから海外で事業を開始する中小企業、または海外展開の再編に取り組む中小企業が対象の融資です。
こちらも日本国内の本社を存続させることや、事業の延長と認められる規模の海外進出であることなど、いくつかの項目を満たした場合に融資を受けられます。
| 資金の使い道 | 事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 |
|---|---|
| 融資限度額 | 直接貸付:14億4,000万円 |
| 代理貸付:1億2,000万円 | |
| 基準利率 | 上限2.5%(年) ※日本とEPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)を発行または署名をしている国で 海外事業展開を行う場合には、4億円を上限として特別利率が適用 |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) |
| ※海外企業への転貸資金 進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合、 その他やむを得ない事情がある場合に限り、以下の返済期間を適用 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 10年以内(うち据置期間5年以内) |
その他の資金制度
スタンドバイ・クレジット制度
日本政策金融公庫では、海外展開支援として国際化に対応する中小企業の海外展開を積極的にサポートしています。
上記の他に利用できる資金制度として、債務の保証と同様の目的のために信用状を発行する「スタンドバイ・クレジット制度」があります。現地流通通貨での資金調達がしやすくなり、日本政策金融公庫と提携する金融機関から長期資金の借り入れも可能です。
海外現地法人等が提携金融機関から現地流通通貨建て融資を受けることを目的としたものであり、令和7年3月末現在、61の地域金融機関と連携しています。
| 補償限度額 | 1法人あたり4億5,000万円 ※海外支店や分工場等、国内親会社と法人格が同一の場合は国内親会社毎に4億5,000万円 ※海外において別個に法人格をもつ場合、当該法人毎に4億5,000万円 |
|---|---|
| 補償料率 | 信用リスク・信用状有効期間等に応じて所定の料率が適用 |
| 信用状有効期間 | 1年以上6年以内 |
| 担保・保証人等 | 担保設定の有無、担保の種類などは応相談 一定の要件に該当する場合、経営責任者の個人保証が必要 |
海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)
国内の親会社と共同で取り組む海外法人に対し、日本政策金融公庫が直接融資する「海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)」もあります。海外の投資先がタイ、ベトナム、香港、シンガポール、フィリピンまたはメキシコと限られていますが、国内の親会社から資金調達をする場合に比べ、送金手続きの必要がなく、場合によっては為替リスクを軽減できる可能性があります。
| 資金の使い道 | 承認等計画を実施するために必要な設備資金および長期運転資金 ※長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含む |
|---|---|
| 融資限度額 | 14億4,000万円 |
| 利率(年) | 4億円までは特別利率(0.95%~1.85%)、 4億円超は基準利率(1.85%~2.75%)が適用 ※信用リスク、融資期間及び担保の有無に応じて所定の利率を適用 ※担保を徴しない場合、利率の引下げ措置あり |
出典:
日本政策金融公庫「海外展開:事業再編基金(国民生活事業)」
日本政策金融公庫「海外展開:事業再編基金(中小企業事業)」
日本政策金融公庫「スタンドバイ・クレジット制度」
日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金(クロスボーダーローン)」
各省庁による補助金・助成金

各省庁では、海外進出企業を対象としたさまざまな補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度を活用することで、資金調達の負担を軽減し、事業展開をスムーズに進めることができます。
厚生労働省
人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)
厚生労働省が提供する「人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)」は、雇用関係の助成金の一つであり、海外進出に特化したものではありません。
しかし、「人への投資促進コース」の中には「成長分野等人材訓練」という、海外関連業務の人材育成にも活用できる訓練費用の助成金が含まれています。Off-JTにより実施される訓練を前提とし、海外の大学院で実施する訓練に対して、中小企業・大企業ともに75%までの助成が受けられます。1人あたりの限度額は、1年度あたり500万円です。
| 対象 | Off-JT(職場外訓練)によって実施される訓練 |
| 経費助成率 | 中小企業・大企業ともに最大75% |
| 限度額 | 1人あたり500万円(海外の場合) |
経済産業省
【JLOX+】クリエイター・事業者支援事業費補助金(クリエイター・事業者海外展開促進)
この補助金は、映像産業振興機構(VIPO)が事務局として交付する補助金制度です。新たな事業環境を見据えて、コンテンツ産業の輸出拡大・海外展開や新市場開拓を促すことが目的です。コンテンツが主体となって海外展開されるものを対象とし、日本ブーム創出を通じた関連産業の海外展開の拡大、訪日外国人等の促進につなげる取り組みに対し補助金を交付することで、日本のコンテンツの海外展開を促進します。
| 対象 | コンテンツが主体となって海外展開を行う事業 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1案件あたり2,000万円、1事業者あたり4,000万円 |
| 補助率 | 対象経費の1/2 |
中小企業庁
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(グローバル枠)
中小企業庁および独立行政法人 中小企業基盤整備機構では、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(グローバル枠)」を実施しています。中小企業や小規模事業者などに対して、海外事業の拡大・強化を見据えた製品・サービスの開発、生産プロセス・サービス提供方法の改善を支援。革新的なサービスの開発・改良に加えて、生産性向上のために必要な設備やシステム投資等の一部を補助します。
特にグローバル枠では、海外市場開拓(輸出)に関する事業に限定して、通常の補助対象経費に加え、海外展開に係る旅費、通訳・翻訳費、そしてブランディングやプロモーションといった費用も対象となります。
| 補助金額 | 100万円~3,000万円 |
|---|---|
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3 |
| 補助事業期間 | 交付決定日から最大12ヶ月(ただし採択発表日から 14ヶ月後の日まで) |
中小企業新事業進出補助金
既存事業とは異なる新しい分野への進出を目指す中小企業を支援します。従業員数に応じて最大7,000万円、特例では9,000万円まで補助され、補助率は一律1/2です。大幅賃上げや付加価値額の増加などの要件を満たす必要があります。
| 補助金額 | 2,500万円~9,000万円(※補助下限は一律750万円) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助事業期間 | 交付決定日から14ヶ月(ただし採択発表日から 16ヶ月以内) |
出典:
厚生労働省「人材開発支援助成金 人への投資促進コース のご案内(詳細版)」
映像産業振興機構「令和6年度補正 クリエイター・事業者支援事業費補助金」
全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」
中小企業庁「中小企業新事業進出補助金」
支援機関別の制度紹介

この他にもさまざまな機関が支援サービスを提供しています。
中小企業基盤整備機構による支援
中小企業基盤整備機構は、国の中小企業政策の実施機関として、起業から成長、成熟期までの成長のステージに応じた支援サービスを行っています。自治体や支援機関、国内外の機関など、幅広い連携を持ち、海外進出にも役立つ支援があります。
ファンド出資
ファンド出資事業は、中小企業基盤整備機構が行う中小企業の資金調達を目的としたファンド組成と出資のための事業です。民間機関などと投資ファンドを組成し、中小企業の資金調達をスムーズにして、経営への踏み込んだ支援を行います。ベンチャー企業やスタートアップ企業の他、既存中小企業の新規事業の展開をサポートしています。
出資事業の種類は3種類。設立5年未満の創業または成長初期の中小企業を支援する「起業支援ファンド」、新規事業の展開や事業再編により新たな成長・発展を目指す中小企業を支援する「中小企業成長支援ファンド」、事業再生に取り組む中小企業を支援する「中小企業再生ファンド」に分かれています。
それぞれのファンドごとに投資対象が異なるため、利用する際にはファンドごとに運営する投資会社の審査を受けることが必要です。
商工組合中央金庫による支援
商工組合中央金庫(商工中金)は、全国47都道府県とニューヨークや上海、バンコクなど海外5箇所に拠点を構える中小企業のための金融機関です。中小企業等の海外進出に向けたサポートを強化するために、日本貿易振興機構との業務の連携強化も図っています。
商工中金で行っているのは、中小企業の海外進出や海外現地法人の事業拡大のための資金融資。内容としては、親会社からの転貸形式にて行う「親子ローン」、現地法人に対して直接貸付をする「現地法人貸付」。また「スタンドバイ・クレジット」による債務保証により、現地金融機関が現地法人への直接融資を可能にする支援などがあります。
海外進出のための融資や現地法人の資金調達の他、輸出入取引に係る貿易決済や海外送金、先物為替予約などの外国為替業務なども利用可能です。
信用保証協会による支援
全国信用保証協会連合会では、「海外投資関係保証制度」や「特定信用状関連保証制度」などがあります。こちらは貸付制度ではなく、融資をサポートする支援制度です。
海外投資関係保証制度
海外投資関係保証制度は、日本国内の中小企業が海外に法人を設立し、金融機関から投資事業資金を受けるための支援制度です。信用保証協会が債務保証を行うことで、海外直接投資事業資金の融資を受けやすくなります。
資金使途は、出資割合が10%以上となる海外法人への出資や貸付、海外支店や営業所の設置、従業員の教育費用などとされています。限度額は2億円で、海外に設立した法人に対する出資や設備投資を行っている、またはこれから行う国内の中小企業が対象です。
特定信用状関連保証制度
特定信用状関連保証制度は、海外子会社が現地の金融機関から融資を受ける際に利用できるサポート制度です。
この制度では、国内金融機関が現地金融機関に発行する信用状に関連して、親会社(国内の中小企業)が負担する債務を信用保証協会が保証することで、現地金融機関からの資金調達を支援します。対象となる資金は、国内中小企業者の海外子会社が現地金融機関から借り入れるもので、限度額は2億円です。
日本貿易振興機構(ジェトロ)による支援
中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成補助金
複数の企業や団体が連携し、輸出支援の仕組み(エコシステム)を構築する実証事業を支援する補助金です。特定地域や分野において、輸出促進のための共同プラットフォームや共同販路開拓事業などを立ち上げる際に活用できます。農産品、ファッション、コンテンツ、サービス産業など、幅広い分野が対象となり、地域全体での輸出競争力強化を目指します。
その他の支援機関
国際協力銀行(JBIC)
国際協力銀行では、新興国市場での独自のビジネス拡大を目指す中堅・中小企業の増加に伴い、多様化する資金ニーズに応える取り組みが行われています。具体的には、民間金融機関との協調融資による個別融資スキーム、民間金融機関を通じたツー・ステップ・ローンスキームなどの資金調達支援、中小企業向けの情報提供や新興国各国の政府や海外地場金融機関との連携などがあります。
東京都産業労働局
東京都で行っている海外展開支援もあります。東京都産業労働局の「東京都中小企業制度融資」では、海外での販路開拓等を考えている中小企業からの資金需要に対応するため、東京都、信用保証協会、金融機関が協力して資金を供給。融資期間は10年以内(据置期間2年以内)であり、海外展開に向けた資金を融資すると同時に、小規模事業者には東京都から信用保証料の2分の1の補助金が支給されます。
出典:
中小機構「ファンド出資」
商工組合中央金庫「公式サイト」
全国信用保証協会連合会「海外展開をお考えの方」
日本貿易振興機構(ジェトロ)「令和7年度「中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成事業費補助金」の公募について」
国際協力銀行「各分野での取り組み/中堅・中小企業分野」
東京都産業労働局「東京都中小企業制度融資」
分野別の特化支援策
海外進出を成功に導くためには、一般的な資金調達だけでなく、地域特性や事業内容に応じた専門的な支援制度を活用することも重要です。
知的財産戦略支援(特許庁・INPIT)
中小企業等海外侵害対策支援事業(特許庁)
海外における模倣品対策や商標トラブルに対応する支援事業です。日本貿易振興機構(ジェトロ)を支援機関として、模倣品の調査費用や商標取消訴訟などの対応費用を2/3、上限400万円まで補助します。
INPIT外国出願補助金(独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT))
海外での特許・商標・意匠などの出願費用を支援する制度です。出願先の国や出願件数に応じて、1事業者あたり最大で300万円の費用が補助され、補助率は1/2です。翻訳費用や現地代理人の費用なども対象となっています。
新興国市場開拓支援(経済産業省)
グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金( 小規模実証・FS事業 )
この制度は、グローバルサウス諸国が抱える社会課題の解決を目指して、日本の企業が現地でインフラ実証や技術協業を行う費用の一部を支援します。現地企業との連携を通じた市場開拓や、日本の技術やノウハウを活かした新興国市場でのビジネスチャンス創出に関する費用を補助します。
デジタル化支援(経済産業省)
貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金
この補助金は、デジタル技術を活用した貿易手続きの効率化を支援する制度で、必要経費の一部を補助します。デジタル化による貿易業務のコスト削減や効率化に取り組む企業向けの制度です。
小規模連携・地域活性化支援(中小企業庁)
小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)
中小企業庁が提供するこの事業は、地域振興等機関が主導し、10以上の小規模事業者(参画事業者)の販路開拓を行う場合に補助されるものです。単なる販路提供に留まらず、事業終了後も効果が継続し、地域全体の活性化に繋がる取り組みが対象で、補助上限額は5,000万円です。
出典:
特許庁「海外侵害対策支援事業」
独立行政法人工業所有権情報・研修館「INPIT外国出願補助金」
経済産業省「貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金」
中小企業庁「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」
資金使途別の制度の選び方

海外進出に向けた資金調達では、何に資金を使うかによって最適な制度が変わってきます。主要な資金使途別に、検討すべき制度を見ていきましょう。
1. 設備投資・拠点設立費用
大規模な投資が必要となる設備投資や海外拠点の設立には、以下の制度が選択肢となります。
- 日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金」
- 日本政策金融公庫「クロスボーダーローン」
- 日本政策金融公庫「スタンドバイ・クレジット制度」
- 商工中金の融資「親子ローン・現地法人貸付」
2. 運転資金・販路開拓費用
日々の事業運営に必要な運転資金や、海外でのプロモーション、展示会出展、ECサイト構築といった販路開拓費用には、以下の融資と補助金の組み合わせが考えられます。
- 日本政策金融公庫「海外展開・事業再編資金」(運転資金)
- 中小企業庁「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(グローバル枠)」
- 日本貿易振興機構(ジェトロ)「中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成補助金」
- 中小企業庁「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」
- 経済産業省「貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金」
3. 人材育成・組織強化費用
海外進出に必要な人材育成には、以下の助成金が利用できる場合があります。
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」
4. 知的財産保護・模倣品対策費用
海外での模倣品対策や商標・特許出願には、以下の制度を活用することができます。
- 特許庁「中小企業等海外侵害対策支援事業」
- INPIT「外国出願補助金」
5. 新規市場開拓・実証事業費用
新興国などでの市場開拓や新しい技術の実証事業には、リスク軽減のため以下の補助金の活用が考えられます。
- 経済産業省「グローバルサウス未来指向型共創等事業費補助金」
- 中小企業庁「中小企業新事業進出補助金」
それぞれの支援団体や事業内容を比較して、自社の事業展開や必要なサポートに応じて選択をしてください。なお、融資・助成金等の制度内容は記事掲載時点(令和7年7月)のものです。最新の制度内容については各機関にお問い合わせください。