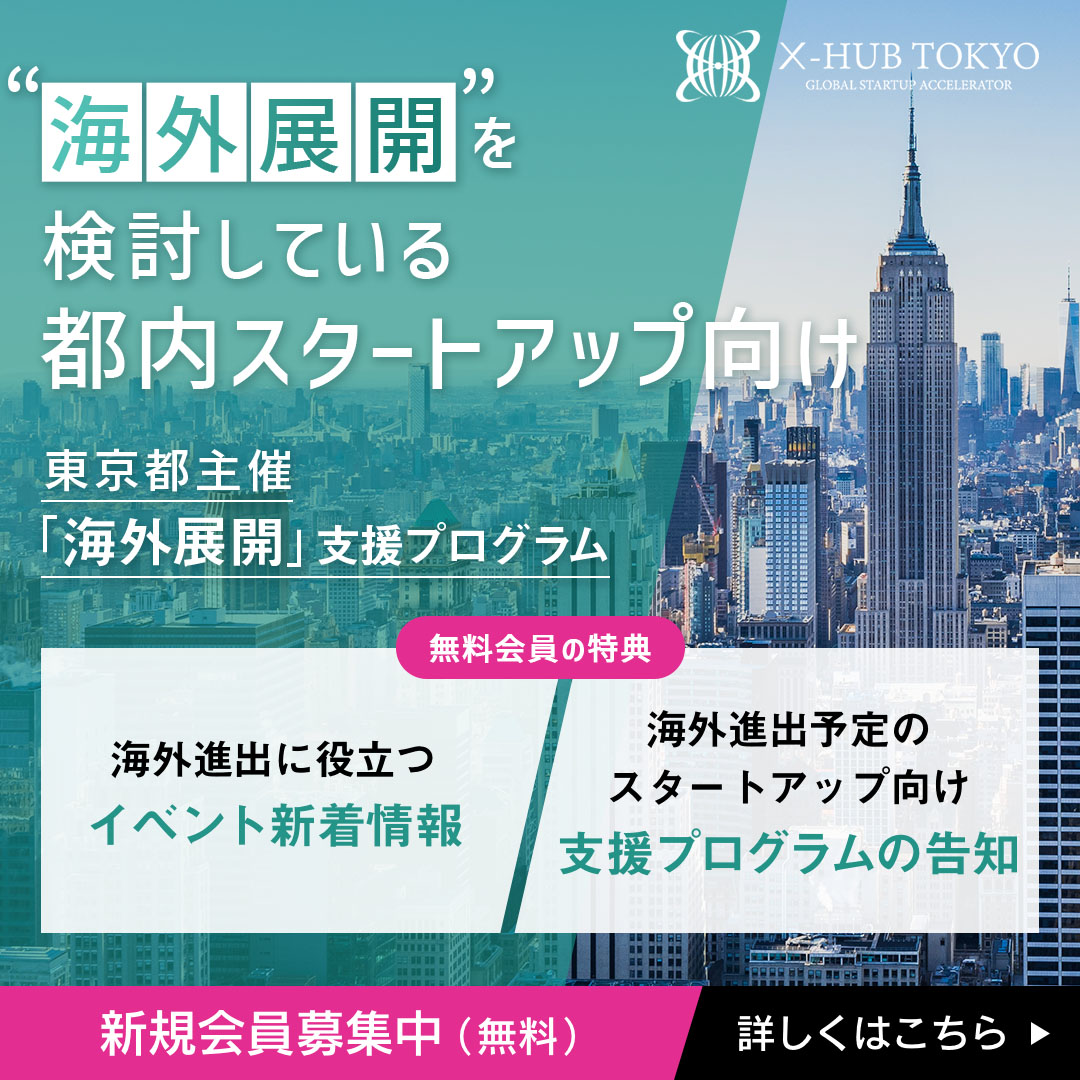税金は国によって課税の有無や額に違いがあります。そのため、海外進出の際には必ず進出先の課税に関する情報を収集しなければいけません。
海外法人の工場や物件などにかかる固定資産税、そして海外進出前に確認すべき日本で所有する固定資産に対する納税手続きについて、そのポイントをまとめました。
目次
日本の「固定資産税」とは
固定資産税は、個人法人に関わらず所有する固定資産に課税される地方税です。課税の対象になるのは土地や家屋、減価償却の対象となる償却資産です。個人で不動産を保有している人であれば固定資産税を支払ったことがある人もいるでしょう。
固定資産税や都市計画税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。この固定資産税評価額は3年に1回見直しになり、市区町村が税額を計算して納税義務者に納税額を通知します。
これらの課税対象物を1月1日に所有している個人、法人に固定資産税がかかります。これは日本国内に不動産を保有している場合に発生する税金です。そのため日本国内に居住し海外赴任で日本を離れていたとしても変わらずに課されます。
アメリカ・中国の固定資産税の扱い

では、海外に不動産を保有している場合はどうでしょうか。海外の固定資産の場合はその国の課税制度に従って税金を納めることがあります。ここでは主要な国の固定資産税について紹介します。
アメリカの固定資産税
アメリカにおいて、法人税は連邦と州レベルでそれぞれ課税されます。州によって固定資産税は扱いが大きく違うので注意が必要です。アメリカでは固定資産税は不動産と動産、無体財産にカテゴリ別に扱われます。不動産はどの州においても課税されるものの、税率には違いがあります。
税額については市場価値に税率を掛けて四半期ごとに徴収される場合が多いです。しかし、動産や無体財産については課税対象とするかどうか州によって違います。機械や装置にも課税する州がある一方で動産、公益施設には課税しないという州もあります。
中国の固定資産税
固定資産税について意外なのは中国です。不動産バブルが到来して不動産の価格が上昇した中国ですが、一部を除いて固定資産税の納付制度はありませんでした。しかし、2019年3月の全国人民代表大会において、李国強首相は立法化を進めるという方針を示します。そして2021年10月の全国人民代表大会では、日本の固定資産税に相当する「不動産税」の試験導入を決め、全国の複数の都市で準備が始まりました。
中国大都市の不動産価格は、ここ10年で平均2~3倍上昇したと言われています。この高騰と連動して、不動産税導入の必要性が叫ばれてきました。しかしながら2023年12月現在、不動産税の導入は見送られています。中国ではコロナウイルス対策の金融緩和により、不動産価格が高騰しました。この高騰を抑えるため、中国政府が導入した不動産・金融の規制強化によって住宅販売数が減少し、不動産市場の低迷が続いていることが理由の一つです。
地方政府の財政安定のほか、格差の是正や不動産の投機取引の過熱化を防ぐためにも、不動産税の導入は避けて通れないという指摘もあります。
ただし不動産税の導入は、不動産価格への影響が免れられません。中国経済が上向き、不動産危機が解消されたタイミングで、不動産税の立法化について再度議論が始まると見られています。中国への進出を意識している企業は、これらのリスクについても想定しておく必要があるでしょう。
参考サイト:日本貿易振興機構(ジェトロ)「税制|米国」
ドイツ・インドの固定資産税の扱い
ドイツの固定資産税
ドイツは外国人による不動産取得を制限していないため、土地やマンションなどを所有することができます。ドイツでは土地と建物を同一としてみなし、不動産というと基本的には土地を指します。建物は土地の付属物となるため、独立した不動産として定義されていません。
ドイツにおける固定資産税に該当するのが不動産税(Grundsteuer)で、個人または事業用の不動産に対して地方自治体から課せられます。税率は不動産のカテゴリによって異なり、カテゴリAは農地や森林、カテゴリBは建物の建設予定地や建築物が存在する土地が対象です。帳簿評価額に対する最終的な実効税率は0.98%~2.84%の間とされています。
インドの固定資産税
インドも日本の企業とつながりが強い国です。インドの固定資産税は、州政府や市当局などの地方自治体の管轄となります。固定資産税は不動産の査定価格に基づいて課され、税率は州によって違いがありますが、一般的に1.0~5.5%程度と言われています。
しかし、インドは土地の取得が難しい国でもあります。インドでは不動産そのものを登記する制度がありません。そこで土地所有者の特定が難しく、土地所有者と取引しようとすると他の者が所有を主張するといったトラブルや訴訟が発生するケースもあります。
また、土地の利用や不動産の権利についても制限があるため、自由に土地を活用できないケースもあります。さらに、インドの土地は外国人の個人所有は認められていません。しかし、外国企業のインド法人や支店などによる不動産購入は可能です。
参考サイト:
経済産業省「各国・地域の税制概要とホットトピックス ドイツ」
経済産業省「インドの税制概要・進出時の留意点」
ASEANの固定資産税の扱い(シンガポール・タイ・フィリピン・ベトナム)

シンガポールの固定資産税
シンガポールでは、その不動産の年間評価額(Annual Value)が政府機関によって算定され、それに応じて固定資産税が発生します。年間評価額(Annual Value)とは、その不動産に対しての一般的な収入額、つまり家賃価格のことを指します。固定資産税の金額は、この「年間評価額」に「その年の固定資産税率」を掛けた金額となります。
年間評価額は、「住宅用不動産」または「住宅用土地及び商業・産業用不動産」によって計算方法が異なります。「住宅用不動産」の場合には、推定総年間家賃(Estimated gross annual rent)をもとに算定されます。「住宅用土地及び商業・産業用不動産」の場合は、推定の市場価格(Estimated gross annual rent)の5%とされています。
続いて、固定資産税の税率です。こちらは、「住宅用不動産」については累進課税制度が用いられ、オーナーが居住しているか否かで税率が変わってきます。オーナーが居住している場合は家賃収入が発生しないため、その分税率は低くなる仕組みです。「住宅用土地及び商業・産業用不動産」の場合には一律で年間評価額(土地の場合は土地評価額の5%)の10%となっています。
シンガポールの固定資産税は1年に1回、毎年12月末に請求され翌年1月末までに納付することとされています。
タイの不動産税制
タイでは土地のほかに建物を別個の不動産として扱います。タイはもともと固定資産税がない国でしたが、2019年3月に新土地家屋法が施行され、2020年8月から「土地家屋税」の徴税が開始されました。農業目的なのか住居目的なのか、土地や建物の利用目的により税率は異なりますが、税率の上限は0.15%~3%までとされています。
ただし、新型コロナウイルスの影響により2022年と2023年は90%もの減免措置が実施され、2024年以降は再度検討となっております。タイの不動産を購入しようと考えるのであれば、固定資産税の動向も注視しておきましょう。
フィリピンの固定資産税
フィリピンでは、設備機械、建物、土地などの固定資産に対して、査定額に基づいた固定資産税を納めなければなりません。土地や建物だけでなく、機械・設備も対象です。税率は自治体によって異なりますが、固定資産評価額に対し2%前後の税金が課せられます。納付方法は一括払い、もしくは3か月ごとの年4回の支払いから選択できます。
なおフィリピンでは、フィリピン共和国憲法によって、外国企業及び外国人による土地の購入・所有は認められておりません。購入できるのは、フィリピン国籍を持つ人、もしくはフィリピン法人に限定されています。
ただし、外資比率が40%以下のフィリピン法に基づいて設立された法人であれば、法人名義で所有することができます。建物の所有については、外資規制がないため、外国企業であっても所有することが可能です。
ベトナムの固定資産税
ベトナムには、日本の税法上で定められている固定資産税に該当する税金はありません。地は国民の共有財産とされ、国が統一的に管理をしています。そのため土地に対する所有権はなく、土地の使用権のみ取得することができ、土地の登記をする場合に登記税が発生します。
固定資産税の代わりに支払いが必要な税金は、土地税と土地の使用料です。土地税は非農地税法によって課せられる税金で、2012 年以降に家屋やアパートの土地について、所有者に対して累進課税が行われるようになりました。この税金の税率は0.03%から0.15%の間で変動します。
土地使用料は、外資系企業などに対して課せられる財産税の一種です。土地使用権の賃借料として徴収されます。通常は土地リース料としても知られており、料率は地域や周辺の産業基盤の整備状況、会社の業種などによっても大きく異なります。
ベトナム政府は、他の国に比べ土地からの税収が低いことから、不動産投機を抑制するために土地と建物に対する税制について改正を検討しています。今後、ベトナム進出を考えている企業は税制改正についてもチェックが必要です。
参考サイト:
日本貿易振興機構(ジェトロ)「税制|タイ」
日本貿易振興機構(ジェトロ)「シンガポール税制の概要【2022年改訂版】」
経済産業省「各国・地域の税制概要とホットトピックス フィリピン」
日本貿易振興機構(ジェトロ)「税制|ベトナム」
日本国内に不動産を所有している場合
納税管理人の選任
海外勤務や海外赴任で1年以上日本を離れる場合、納税者本人に代わって税金を納める「納税管理人」を選任しないといけません。その申請をすることで、所有者を変更することなく納税通知書を納税管理人宛に送付してもらうことができます。
「納税管理人申告書」もしくは「納税管理人承認申請書」は、所有する固定資産のある市区町村への届け出が必要となります。この手続き以降、納税管理人は書類の受け取りや、税金の納付・還付の手続きなどの一切の事務処理を行うことが可能です。変更や解任の場合にも届け出を忘れないようにしましょう。
なお、納税管理人自体に納税の義務は生じません。万が一、納税者の滞納によって財産の差し押さえが発生したとしても、納税管理人には連帯して納付する義務はないこともお願いする際には伝えおくと安心でしょう。
納税通知書が手元に届く前に出国の予定がある場合には、とくに注意が必要です。納税管理人は国内居住者であれば個人や法人という決まりはなく、税理士に依頼するケースも多いようです。なお出国前に課税された年度分を全額納税された場合には、この手続きは不要となります。
「納税管理人申告書」と「納税管理人申請書」の違い
納税管理人となる方の住まいが、所有する固定資産と同じ市区町村の場合には「申告書」、所有する固定資産とは異なる市区町村の場合には「承認申請書」となります。ただし東京都のように申告書と承認書を分けていない場合もあるので、提出先に合わせて用意をしましょう。
※東京23区内の提出先は該当の土地・家屋を所轄する都税事務所、もしくは都税証明郵送受付センターと決められていますので、詳しくはこちらをご参照ください。
参考サイト:東京都主税局「納税管理人申告のご案内」
まとめ
法人が海外で不動産を取得する理由は、生産工場を取得したり拠点となる営業所を設立したりと様々です。しかし、その国の税制や制度を知らずに購入してしまうとトラブルのもとになってしまうことも多々あります。不動産の取得を検討するときには、制約や発生する税金について細かく調べておくようにしましょう。
また海外進出のタイミングでは、日本で所有している不動産について後回しになりがちですので、事前に手続き済ませておくことをオススメします。