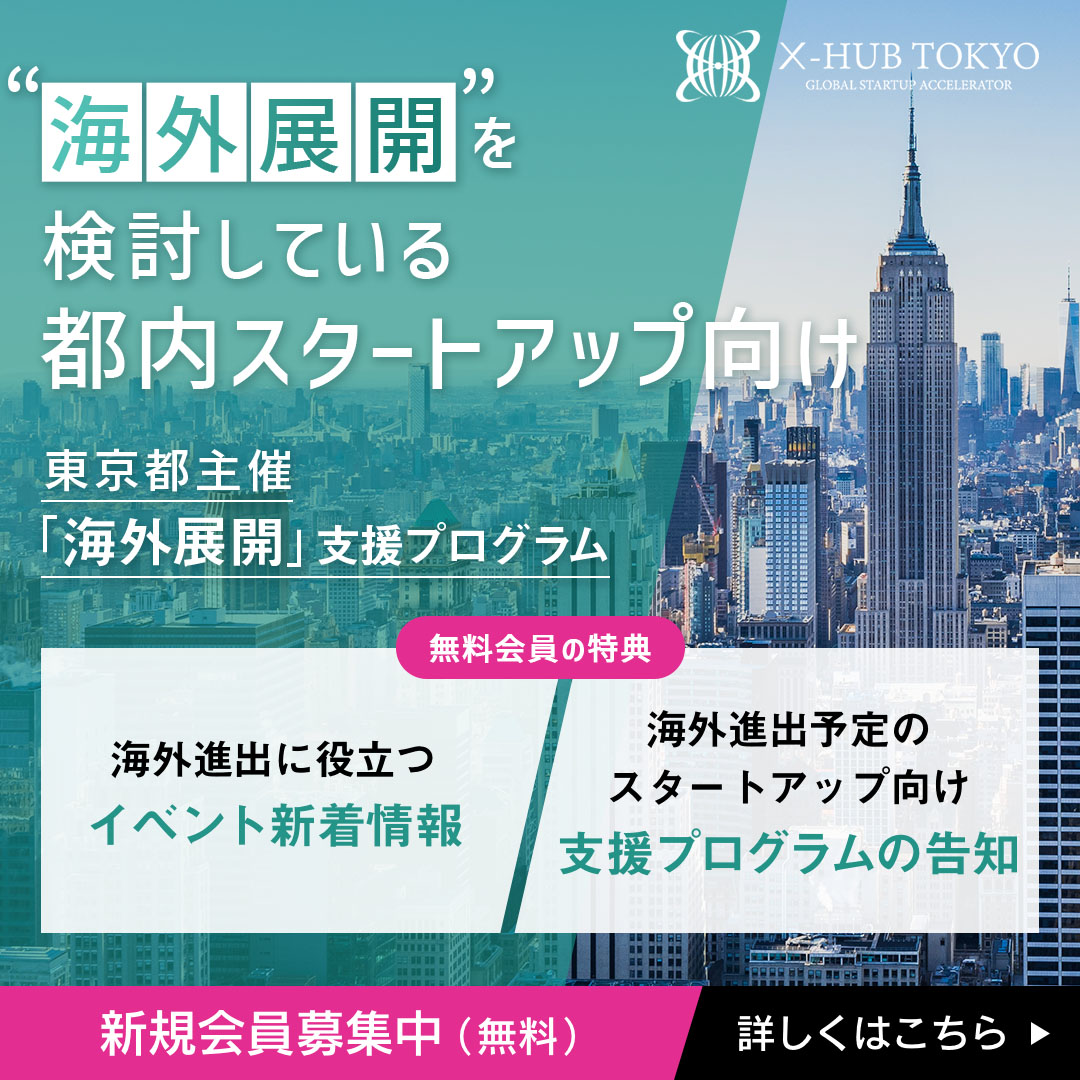2000年代の世界経済は、サブプライムローン問題の表面化やリーマンショックなどを背景に波乱に満ちていました。アメリカ経済の変遷と特徴、これからの向かっていく方向性について調べました。
目次
第一次世界大戦後のアメリカ経済の変遷
現在からおよそ100年前となる1919年はヴェルサイユ条約が締結された日です。2018年は第一次世界大戦終結の1918年から100周年として、大規模なイベントも世界中で開催されました。第一次世界大戦が終結してからも世界では第二次世界大戦、東西冷戦、ソ連の崩壊などの歴史的事件が発生しています。
世界経済の中心はイギリスからアメリカへ
第一次世界大戦後の大きな変化として、はじめに注目すべき点は、世界のトップ国の移り変わりです。世界経済のトップはイギリスからアメリカに移行しています。これをGDP(国内総生産)で確認してみましょう。
もともとアメリカは第一次世界大戦よりも前の段階でイギリスの実質GDPを抜いていました。アメリカではこの時代に人口が大幅に増加して、GDPの上昇を助けたのです。中産階級が増えて内需中心の経済が成立していました。しかし、第一次世界大戦が勃発することで、ヨーロッパ諸国への軍事製品の輸出が増えて鉄鋼や小麦の輸出が盛り上がりました。
一方で、産業が豊かになり株価が上がり続けてピークアウトしていくと、ついに1929年には世界恐慌が起こります。1930年代はアメリカにとって長期的な不況が続きますが、それを脱するきっかけとなったのが第二次世界大戦の勃発でした。
第二次世界大戦とアメリカの安定成長
第二次世界大戦を通じて実質GDPが増大
1939年はナチスドイツがポーランドに進行して第二次世界大戦の火ぶたが切られた年です。戦時中は軍需品の生産が拡大、さらにそれに伴う財政出動がおこなわれ、結果として第二次世界大戦を通じてアメリカは大恐慌から抜け出すことに成功しました。
例えば、軍需製品の需要が増したことによって600万人の女性が加工生産分野で仕事を得ました。1945年の実質GDPは開戦時の1939年と比べて約88%増大し、さらに失業率も労働力の1.2%まで低下しました。
アメリカドルが世界の基軸通貨に
また、1944年のブレトンウッズで開かれた連合国通貨金融会議ではアメリカのドルが基軸通貨となりました。すでに世界一の経済力と軍事力を持つアメリカの通貨ドルは、世界でもっとも流通量が多く、信用力がある通貨だと判断されたのです。このドルを基軸通貨とする通貨制度がブレトンウッズ体制です。
ブレトンウッズ体制になってからは、世界中でドルが流通するようになり、世界各国はドルを買って貿易しました。当時の為替は固定相場制なので、現在の変動相場制と違って為替変動を気にすることもなく輸出に力を入れることができたのです。
戦争後には経済の再転換が求められます。アメリカの戦後経済への転換は比較的スムーズでGDPが一時的に低下したものの、順調な経済成長を遂げます。
アメリカの経済発展を支えた保護貿易

第二次世界大戦後、冷戦やキューバ危機などもありましたがアメリカは安定した成長を続けます。1960年代にはホワイトカラーがブルーカラーの数を凌駕し、人々の生活水準は飛躍的に向上しました。ハリウッド映画やテレビなどでもアメリカの生活様式を世界に発信して、多くの国がそれに追いつくようにと経済発展を目指したのです。
この時期は製品のコストダウンの影響もあって大量消費社会が本格化しました。また日本にとっても自動車や家電製品を武器に世界に進出し始めた年です。1980年代には対日貿易赤字が増加して頻繁に貿易摩擦が報じられるようになりました。
これは日本に限ったことではありません。アメリカは1950年代まで世界の鉄鋼生産量の40%を占めていました。しかし、1960年代に日本やヨーロッパでの生産が増えたのです。その結果アメリカでは保護貿易の要請が高まり、製造業など輸出産業は厳しさを増しました。
保護貿易で期待される内需拡大
保護貿易とは、国家が外国からの輸入品に対して高い関税を課したり、数量を制限したりすることで、国内産業の保護や自国の雇用を守るための貿易政策です。1994年のクリントン政権のもとでは特定産業を保護する政策がすすめられ、特にハイテク産業に注力されています。また、リーマンショック後には多くの国が保護貿易の方向に進もうとしました。
保護貿易政策は保護された産業に対しては一時的に利益をもたらします。しかし、産業の国際競争力を下げることもあるため注意が必要です。保護貿易で経済成長が促進された例としてはアメリカ西部開拓時代がよく挙げられます。
もともと国内経済の規模が大きければ保護貿易をおこなっても内需主導での成長が期待できるでしょう。トランプ元大統領の保護貿易路線もこのようなアメリカの経済成長の延長線上にありました。
トランプ政権下におけるアメリカの経済政策
アメリカ第一主義(アメリカ・ファースト)
トランプ氏は大統領就任後、選挙戦から主張をしてきたアメリカ第一主義(アメリカ・ファースト)を鮮明に打ち出しました。具体的には、他の国からの輸入品に高い関税をかけ値段を上げることで、アメリカ製品を売りやすくするような保護主義的な貿易政策を次々に進めたのです。
アメリカ国内の労働者やその家族の利益のためにと、海外からの農産品や工業品の輸入を減らし、アメリカ製品の国内流通を増やしました。企業に対しては、海外に移転した工場をアメリカ国内に戻し、アメリカ人を雇用することを求めました。
中国との貿易摩擦
アメリカ最大の輸入相手国である中国に対し、トランプ元大統領は貿易赤字の解消を目的として、中国からの輸入品(鉄・ロボット・半導体など1000品目以上)を対象に次々と関税の上乗せをはじめました。2018年の終わりには、家具や家電を含む中国からの輸入品のほぼ半分に対して最大25%の関税上乗せ、さらに2019年6月には中国からの輸入品のほぼ全てが対象となりました。
トランプ元大統領が次々と発動する関税の引き上げによって、逆に中国から報復措置としてアメリカ産の製品(大豆や牛肉などの食料)に高い関税をかけられたりと、まさに報復合戦となりました。当初は工業製品が対象でしたが、中国製の身近な生活用品も関税上乗せの対象にしたことで、結果的に値上がりという形でアメリカ国内の家計を圧迫することにもなったのです。
このように「アメリカ・ファースト」を掲げたトランプ元大統領は制裁関税を相次いで発動し、さらに情報流出や安全保障上の懸念があるとして中国通信機器大手などの中国企業とアメリカ企業との取引を原則禁止する規制も導入しました。
新型コロナウイルス後のアメリカ経済
トランプ政権からバイデン政権へ
新型コロナウイルスの混乱により大恐慌以降最悪と言われるほど景気の悪化したアメリカ。それに伴ってトランプ元大統領の支持率は低下しました。2021年に発足したバイデン政権、バイデン氏はトランプ元大統領とは真逆のキャリアを有する人物です。36年に渡る上院議員のキャリア、そしてオバマ政権で8年間の副大統領という公職経験、バイデン政権は新型コロナウイルス対策や経済再生といった国内の立て直しからスタートしました。
2021年のアメリカ経済は、2020年と同様に新型コロナのウイルス感染状況に振り回されたと言えるでしょう。市場の事前予測(8.5%程度)を下回ったものの、2021年4〜6月期に実質GDP(国内総生産)がコロナ前の水準に復帰します。しかしその後新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、夏頃には成長率が鈍化しました。それでも2021年の実質GDP成長率は前年比+5.7%の高水準となりました。
続く2022年では、急速に進行するインフレや金利上昇にもかかわらず、実質GDP成長率が前年比2.1%と潜在成長率並みの成長を記録しました。個人消費、特にサービス消費がプラスに寄与し、サービス消費に大部分を支えられた経済成長でしたが、インフレの進行により先行きには不透明さが残りました。
加速するインフレ
コロナショックから景気が急回復したアメリカでは、加速するインフレが問題となりました。コロナ禍で停滞していた経済活動が再開することで、需要が急激に高まりインフレを引き起こしたのです。
記録的なインフレの背景には、深刻な人手不足が関係していると言われています。アメリカの2022年2月時点の新型コロナウイルス感染者数が約7,860万人、死者数は約94万人と世界で最も多い数字となっていました。人手を確保するための賃金の引き上げが、結果的に商品やサービスなど物価の引き上げにつながったのです。
人口構成の変化・移民の問題
近年、アメリカ経済の問題の一つに、少子高齢化による人口構成比の変化があります。平均寿命の延長や出生率の低下によって、アメリカの人口構成は高齢化しています。日本に比べるとまだまだ低いものの、高齢者が増えることで医療や介護などの費用が増大し、社会保障制度に大きな負担がかかることが懸念されているのです。
一方、移民の問題もアメリカが抱えている課題の一つです。アメリカの移民問題は、経済政策と密接に結びついています。長らくの新自由主義的経済政策により、アメリカは外国からの移民を受け入れ、経済成長に貢献してきました。しかし、同時に不均衡な富の分配や社会格差が拡大し、中間層の苦境を引き起こしているのです。
新型コロナウイルスの混乱によって、人口問題と移民問題がより複雑化しています。多くの移民労働者が失業し、経済に深刻なダメージを与えました。移民問題は政治的にも大きな問題となっており、移民政策が変更されるたびに社会や経済に大きな影響を与えることもあります。バイデン政権は、移民政策において新しい方針を模索し、合法的な経路の整備や不法移民の処遇に対する姿勢の見直しを行っています。
アメリカ経済の今後
2023年のアメリカ経済は、急激なインフレに対応するため、FRB(米連邦準備制度理事会)による金利利上げがなされました。これにより経済活動が鈍化したものの、輸入物価や生産者物価が落ち着いたことで、景気減速に歯止めを掛けることができました。
経済政策の正当性と実績をアピールするバイデン大統領は、2024年秋の大統領選挙に向け、再選を目指し選挙活動をスタートさせています。
バイデン大統領が提唱するバイデノミクス
「バイデノミクス」とは、バイデン大統領が提唱し、実施している経済政策の枠組みを指します。もともとはバイデン政権を批判的に論じるために使われていた言葉ですが、バイデン大統領はこれを逆手に、大統領選に向けたスローガンとして積極的に打ち出しました。
バイデノミクスはアメリカ経済の再建と持続可能な成長を促進するために設計された経済政策であり、社会的な公平性と環境への配慮を重視しています。2021年に発表した経済政策の中核的な要素を含んでおり、中間層の拡大と低所得層の底上げを目指す、次のような特徴があります。
1.インフラ投資拡大と雇用の創出
アメリカ国内の老朽化した基本的なインフラの整備と向上に焦点が当てられています。具体的には、道路・橋・港湾・空港などの交通インフラの改善、そしてデジタルインフラの拡充が含まれます。また、国家安全保障や競争力を高めるために、半導体の国内生産などの戦略的な分野への投資も含まれています。
2.教育による労働者の能力向上
アメリカの労働力を強化し、競争力を高めるために教育や訓練への投資が行われています。労働者のスキル向上や職業訓練プログラムの拡充が含まれ、これによって雇用の創出と高賃金の職を増やすことが狙いです。また、労働組合の支援も行われ、働く人々の権利向上が目指されています。
3.競争促進に伴うコスト減で中小企業を支援
競争を促進し、市場の健全な競争環境を整えることを重要視しています。大企業による市場支配を防ぐための規制や、中小企業を支援する政策が導入されています。これにより、価格競争が促進され、消費者や中小企業が利益を享受できる環境を構築することが目的です。
今後の見通し
バイデン政権は、中・低所得者層の底上げによる経済再生を目指しており、富裕層を優遇したトランプ前政権を批判しています。さらにアメリカで40年前より提唱された、富裕層や大企業が潤うことで、低所得者層にも恩恵の滴が行き渡るとする経済理論「トリクルダウン政策」も失敗だと主張しています。富裕層ではなく、中・低所得者層に軸足を置く経済政策がアメリカの経済成長率をどのように引き上げるのかにも注目が集まります。
また、トランプ政権から続いている米中貿易摩擦問題についてアメリカ第一主義を改めるとしていますが、トランプ政権が発動した追加関税は維持する方針を示しています。今後も販売先・仕入先の見直しや生産拠点の移転など、米中貿易が世界の金融市場に影響を与える展開は当面続くと見込まれますので、注視が必要です。
まとめ
アメリカ経済の変遷を見ていくと、アメリカが保護貿易による利益を獲得してきた構図が理解できるでしょう。バイデン大統領が示したとおり、今後もアメリカは保護主義的な姿勢で各国と貿易協議を進めていくことが見込まれています。これは海外進出を目指す企業にとってはリスクにもなりえます。
海外進出を目指す場合は、海外市場に詳しく、その事業の展望や将来性などを客観的に評価してくれるコーディネーターやパートナーを探すことをオススメします。