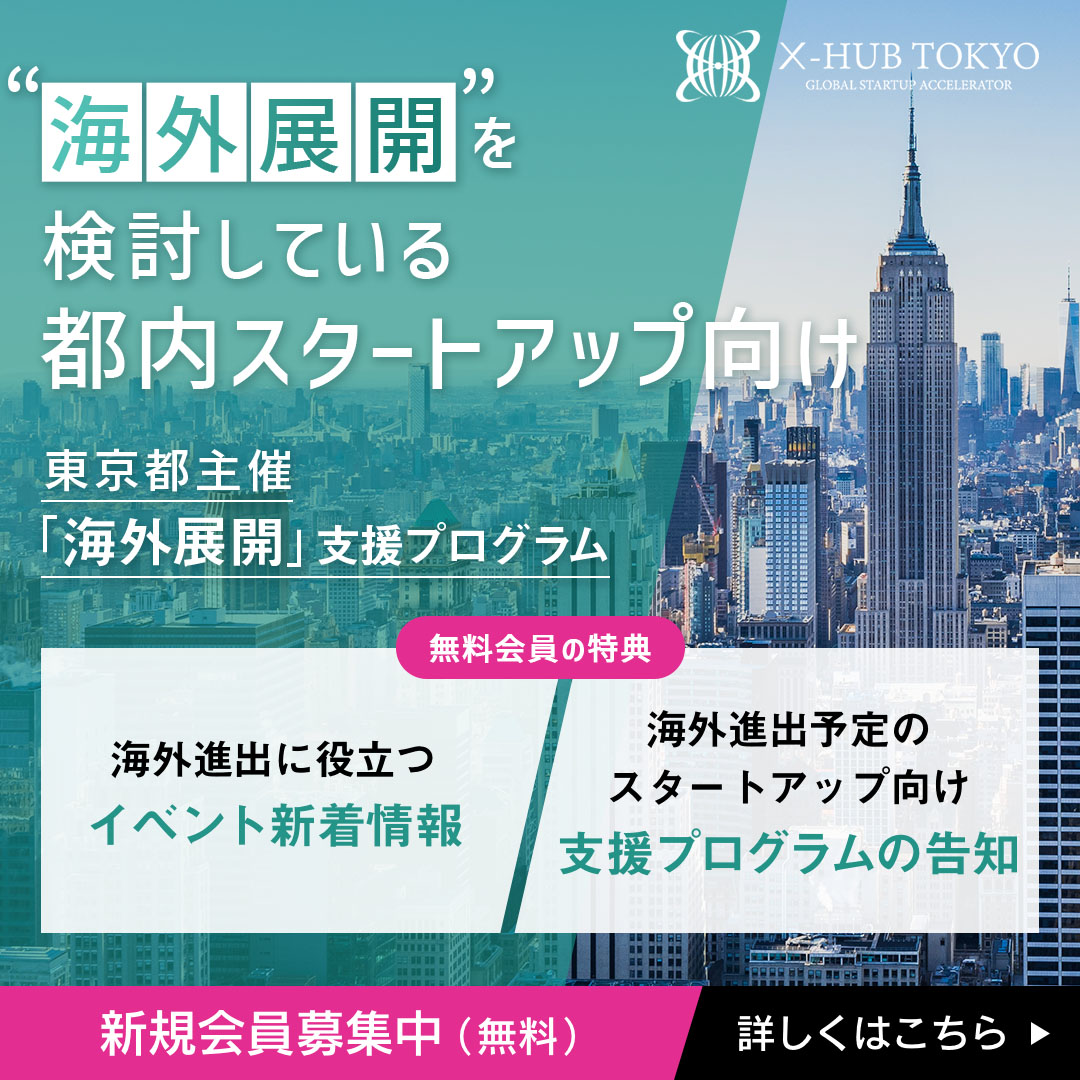日本企業の海外進出は、これまで大企業を中心に進められてきましたが、近年は中小企業やスタートアップ企業にも広がりを見せています。もっとも、進出状況は業界や地域によって差があり、必ずしも一様ではありません。
本記事では、最新の統計や調査結果をもとに、日本企業の海外進出の現状、進出が盛んな業界や地域、リスクや課題、そして越境ECなど新たな展開手段について整理します。
日本企業の海外進出動向

まずは最新統計から、日本企業の海外進出の全体像を確認します。
日本企業の海外進出は、かつて拡大基調にありましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により減少に転じました。外務省「海外在留邦人数調査統計」によれば、2019年には海外在留邦人が141万人を超えて統計開始以来最多を記録しましたが、2020年以降は減少が続き、2024年10月1日時点では129万3,097人と、前年(129万3,565人)からほぼ横ばいとなっています。
日本貿易振興機構(ジェトロ)が公表した「2024年度 海外進出日系企業実態調査」では、日系企業の約6割が黒字を見込むと回答し、収益環境の改善が見られます。地域別では、中国やタイでの拡大意欲が後退する一方、インドやUAEをはじめとする南西アジア・中東、さらにアフリカでは拡大意欲が強まっています。欧州では拡大意欲が過去10年間で2020年に次ぐ低水準となっており、事業拡大に対して慎重な姿勢が目立つなど、全体として地域分散の傾向が強まっています。
また、経済産業省「海外事業活動基本調査(2023年度実績)」によれば、日系現地法人の売上高は約374兆円と前年度比3.5%増加しました。一方、常時従業者数は約532万人と前年度より4.6%減少しており、製造業の雇用減が影響しています。ただし、非製造業では微増となっており、サービス関連分野の堅調さが見られます。
全体として、日本企業の海外進出はコロナ禍以前の水準に完全には戻っていないものの、回復傾向が見られ、地域や業種ごとの特徴を踏まえた戦略的な展開が進んでいます。
海外進出の多い業界

こうした全体動向を踏まえ、ここからは業種別の進出状況を見ていきます。
経済産業省「海外事業活動基本調査」によると、拠点数の多さが目立つのは製造業や卸売業・小売業です。自動車や電機、機械などの大手企業は海外工場の設立や現地生産体制の強化を目的として拠点を構え、製造業の比率は依然として高水準を維持しています。同調査によれば、現地法人数において製造業は全体の約4割を占めており、引き続き中心的な役割を果たしています。
近年はこれに加え、IT・スタートアップ分野やサービス業の進出が拡大しています。クラウドサービスやフィンテック、EC関連などの事業展開を目的に法人を設立する事例が増えており、とくにアジア諸国ではエンジニア人材の確保やコスト優位性を背景に進出が進んでいます。
さらに、飲食をはじめとする日本食関連産業や外食分野では、海外での市場拡大が続いています。農林水産省の「海外における日本食レストラン数の調査結果」によると、世界の日本食レストラン数は2023年時点で約18万7,000店に達し、2021年から約2割増加しました。これは、日本食ブームの広がりを背景に、日系・非日系を問わずレストラン数が増加していることを示しており、日本企業による食材の輸出や外食チェーンの海外展開を後押ししています。実際、主要外食企業の中にはアジアや北米を中心に店舗数を拡大する動きが見られます。
一方、アパレルは競争環境が厳しく、国・地域によって進出ペースに差が出ています。今後は、従来型の製造業に加え、デジタル関連や飲食、美容・ヘルスケアといった生活サービス分野が日本企業の海外展開をけん引する可能性が高まっています。これは、アジア諸国をはじめとする海外市場で、中間層の拡大や生活水準の向上に伴い、日本の質の高い生活関連サービスへの需要が高まっているためです。
このように、業種によって進出の方向性は異なりますが、全体として多様な分野で海外展開の動きが活発化しています。一方で、規制や事業特性の影響により、海外進出が相対的に限られる分野もあります。
海外進出が少ない業界
ここでは、制度面や事業特性の性質上、海外展開が限定される分野を見ていきます。
医療・教育・金融といった分野は、多くの国で外資規制や参入ライセンス、出資比率の上限が厳格に定められており、日系企業の参入は限定的です。とくに医療・介護サービスは、現地資格の取得や制度適合が必要となるため、展開はごく一部にとどまっています。
ただし、教育分野では対面型の進出は依然として制約が大きいものの、オンライン学習や日本語教育など、デジタルを活用した形での海外展開がアジア諸国を中心に拡大しています。日本語学習アプリやオンライン授業など、物理的な拠点を持たずに海外市場へアクセスするビジネスモデルが増えており、従来は参入が難しかった分野にも新たな可能性が生まれています。
また、国内志向の小規模小売、建設業、理美容、クリーニングや清掃といった生活関連サービスは、海外で事業を行う前提がそもそも少なく、現地の文化・商習慣や需要に適応しにくい傾向があります。そのため、こうした分野では海外拠点の設立よりも、国内での事業強化や輸出による間接的な海外展開が主流となっています。
業界・国ごとの海外進出の魅力と優位性

進出が容易でない業種がある一方で、業界や国ごとに見ると、海外進出の優位性が発揮される分野もあります。
まず製造業では、現地の労働力や原材料を活用することでコスト削減と現地需要の取り込みが可能です。アジアでは自動車や電子部品の生産体制が整備され、サプライチェーン強化にもつながっています。
次にIT・通信分野では、技術人材の確保が進出の大きな動機となっています。ベトナムやインドではITエンジニアの育成に注力しており、優秀な人材を確保しやすい環境が整いつつあり、開発拠点やグローバル人材ハブとしての魅力が高まっています。
一方、小売・消費財分野では、市場の成熟度や消費者嗜好に応じて戦略が分かれます。中国は依然として巨大な消費市場が魅力であり、アパレル・日用品・化粧品などの分野で需要を見込んだ展開が続いています。ただし、模倣品対策や競争激化への対応が課題であり、特に近年はEコマースチャネルの重要性が高まっていることから、オンライン展開が成功の鍵となっています。
先進市場である米国では、日本食ブームや健康志向の高まりを背景に食品関連の進出が拡大しています。多様な嗜好に合わせた味やサイズ、パッケージの最適化に加え、食品安全基準や表示規制への対応、信頼できる流通パートナーの確保が成果を左右します。
このように、業界と進出先の国・地域の特性を見極め、その組み合わせから生まれる優位性を設計することが重要です。あわせて、サプライチェーンの最適化やデジタル化の加速といった世界的な潮流を踏まえ、現地の社会・経済環境を継続的にモニタリングしながら柔軟に戦略を見直す姿勢が、今後の成否を左右するでしょう。
業界ごとの海外進出のリスクと注意点
海外進出には大きな魅力やビジネス上のメリットがある一方で、国や業界ごとに異なるリスクも存在します。これらのリスクを十分に理解し、進出先や展開方法を慎重に検討することが重要です。
業界・地域別リスクの具体例
製造業では、ベトナムなどで人件費の上昇や都市部の労働力不足が進み、従来のコスト優位性が薄れつつあります。このため、生産拠点を内陸部へ移転したり、自動化への投資を進めたりする企業が増えています。中国においては、外資規制やデータ規制の強化、地政学的リスクが進出企業にとっての大きな懸念材料となっています。こうした状況を受け、中国以外にも生産拠点を設けてリスクを分散する「チャイナ・プラス・ワン」戦略の動きが加速しています。
サービス業やIT分野では、人材の流動性が高いことによる技術流出リスクや、知的財産権保護の脆弱さが課題です。独自のビジネスモデルやソフトウェアなどの無形資産が現地従業員を通じて模倣・流出するおそれがあるため、進出企業は機密情報の管理や従業員教育を徹底する必要があります。一方、小売業では、現地の商習慣や消費者嗜好の違いによる市場適応の難しさがあり、十分な市場調査と信頼できる現地パートナーとの協業が鍵となります。
市場成熟度に応じた展開戦略
海外進出を検討する際は、ターゲット市場の成熟度に応じた戦略が必要です。米国や欧州などの先進市場では、消費規模が大きく高付加価値を狙いやすい一方、法規制対応や訴訟リスク、コンプライアンス体制の整備などに伴い、事業運営コストが上がりやすいという特性があります。これに対して、ASEANやインドをはじめとする新興国市場では、制度整備が途上である反面、成長ポテンシャルが高く、比較的柔軟な事業展開が可能なケースもあります。
ただし、インフラ水準、人材確保、法制度の整備状況は国によって大きく異なります。そのため、自社の業種や事業モデルに最適な進出先を慎重に選定することが重要です。
海外進出を考えない企業も
日本から海外進出を検討する際には、資金・人材・ノウハウの確保など、さまざまな課題を乗り越える必要があります。これらの条件を満たすことが難しく、結果として進出を見送る企業も少なくありません。
特に中小企業では、現地法人の設立や管理にかかるコスト負担が大きく、経済的にも人的にも国内事業の維持に注力する傾向が見られます。また、製造業の中には「メイド・イン・ジャパン」にこだわり、品質やブランド価値を守るために国内生産を重視する企業もあります。
さらに、海外に拠点を設けずとも、輸出や越境ECを通じて海外市場を取り込む方法を選ぶ企業も増えています。このように、海外進出を考えないという選択も、経営資源やリスク許容度を踏まえた戦略的な経営判断の一つとして位置づけられます。
越境ECの可能性

物理拠点の設置を伴わずに海外需要を取り込む手段として、越境ECの活用が注目されています。
越境ECとは、グローバルECとも呼ばれ、国境を越えて商品やサービスを売買することを指します。具体的には、「Amazon」のような多言語対応のECサイトや自社のECサイトなどを活用し、世界中の消費者とEC取引を行います。
越境ECのメリットは、日本から海外の大きな市場に参入が可能であることです。さらに、国内に比べて需要が高い商品であれば、より大きな利益を得ることもできるでしょう。また、国内市場に比べて競争が少ない場合があるため、市場の拡大が期待できることも越境ECのメリットとして挙げられます。
経済産業省「電子商取引に関する市場調査(2024年版)」によれば、日本のBtoC-EC市場は約26兆円に達し、米国や中国との越境取引額も拡大しています。とくに化粧品や食品、ホビー関連商品は海外での需要が高く、日本ブランドとしての競争力を持ちます。
ただし越境ECにおいては、言語や文化の違いに対応する必要があるため、販売先の国や地域に合わせたマーケティング戦略を策定しなければなりません。また、関税や輸入規制など、国際取引特有の問題も存在します。これらの問題をクリアするためには、十分な市場調査を行うこと、専門知識をもったパートナーの協力を得ることが欠かせません。
まとめ
全体として、日本企業の海外進出はコロナ禍以前の水準には戻っていないものの、回復傾向が明確となり、製造業・卸売業に加え、IT・サービス、飲食といった多様な業界や地域で新しい展開が進んでいる状況です。
重要なのは、世界的なトレンドを踏まえつつ、自社にとって海外展開がどのような意味を持つのかを検討することです。その上で、現地の特性を見極めた段階的な進出や、リスクの少ない越境ECの活用など、自社に適した手段を選ぶことが望まれます。
出典:
外務省「海外在留邦人数調査統計」
日本貿易振興機構(ジェトロ)「2024年度 海外進出日系企業実態調査(全世界編)(2024年11月)」
経済産業省「海外事業活動基本調査(2023年度実績)」
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」
農林水産省「海外における日本食レストラン数の調査結果(令和5年)の公表について」